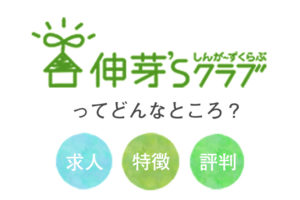こんにちは!保育士くらぶ編集部です。
保育士くらぶでは、保育現場で明日から使える最新トピックや保育士さんの転職、キャリアをサポートするコンテンツをおとどけしています。
求人情報や転職・キャリアのご相談は同グループが運営する「保育求人ガイド」をご覧ください。
今回は、保育士さんたちが子育てと仕事の両立をどうしているか、体験談や大変なこと、準備しておくことをまとめました。
子育てと保育士の仕事の両立を考えている人や、既に両立している人悩める保育士さん必見の記事です!
子育て中の保育士さんの現状
出産を機に保育士をやめてしまう人は多い
結婚・出産を機に保育士の仕事をやめてしまう人はとても多いです。
出産を前にして先輩や同僚がどんな選択をしてきたのか、現職として働いていてどんな仕事環境かということがわかっている以上、子供がいながら働くのは難しいとみなさんやめてしまいます。
他理由も多く含まれていますが、日本には現在保育士の資格は持っているが保育の職に就いていない、いわゆる潜在保育士の数は70万人に上ると言われています。
また産休育休が取りづらいという職場も非常に多いのも理由の一つです。
産休・育休を取れても、いつ復職するか考えてしまう
たとえ産休、育休を取れたとしてもどのタイミングで復帰するかは考えものです。
働いている間に親や家族など子供の面倒を見てくれる人が身近にいなければ、保活をして保育園にいれなければなりませんし、フルタイムで働く場合は延長保育ができるところを探さなければなりません。
グラフから見る「子育てとの両立」
「夫は外で働き、妻は家庭を守る」、専業主婦が当たり前だった日本の家庭のあり方が変わり始めたのは1980年~1990年頃です。
年号が変わり「平成」となった20世紀末には、共働き世帯の数が専業主婦世帯の数を上回りました。

今では、共働き世帯は専業主婦世帯の2倍近い数になっています。
それでも、子育てと保育士として働くことを両立するのは簡単なことではありません。
平成30年度東京都保育士実態調査によると、保育士を辞めた理由を「子育て・家事」と回答した人は13.5%
1割以上の保育士さんが子育てと仕事の両立が難しいと感じていることがわかります。
保育士の子育てが大変な理由

理由①保育園に入れることができない
子育てと仕事の両立が難しい理由はいくつかあります。
平成30年度東京都保育士実態調査で紹介されている、保育士さんの体験談をいくつか挙げてみましょう。
こちらの方は、お子さんを保育園に入れることができないため働けないと回答しています。
時間が経てば経つほど現場での経験を忘れてしまいそうな気がして復帰への不安も年々大きくなっています。
理由②パートタイム・時短勤務で働きたいが現状スポット的な募集が少ない
また、パートタイムや時短での勤務ができれば働きたいという人も少なくありません。しかし仕事の職種柄どうしても週5日勤務であったりフルタイムであったりすることが多く、また短時間であっても夜までの募集であったりすることが多いです。
子どもや家庭を犠牲にしてまで働くことに対して不安があるが、空いてる時間に働きたい気持ちもある。
理由③保育士の処遇が見合っていない
保育士の待遇自体が改善されなければ、職場復帰は難しいとの意見です。この問題は、子育てとの両立という問題だけでなく保育士不足という現状とも深い関わりがあります。
毎日休憩とは名ばかりの、子ども達がお昼寝している中保育日誌を書いたり、現場から離れる時間がなく、リフレッシュする時間もないまま、日々の保育に追われていると思う。
お給料の改善や職場環境の改善をして保護者が働いている間安心して預けられる園が理想である。
理由④子育て中の人には続けにくい職場環境である
子ども優先での勤務ができる職場環境があれば、ワーキングマザーに理解のある職場を求める声も多いです。
また自分の子どもに負担をかけるようなら仕事はできないと思っている。
子どもを1番に考えたいので。
わがままかもしれませんが、子どもの行事、急な病気に臨機応変対応してもらえるとはたらきやすくなるのではないかと思います。
子育てしていても保育士として働きたい!そんな時は・・・
解決策 ①産休、育休制度を使う

子育てと仕事の両立にはいくつか越えなければならないハードルがあることは分かりました。
ここからは、その問題点をクリアするための解決策を考えていきましょう。
まずは、産休・育休制度を利用することです。
産休・育休制度とは?
産休とは、出産の際に女性労働者が休暇を取る制度で、産前休暇(出産の準備期間)と産後休暇(産後に回復する期間)とがあります。
一方、育休(育児休暇)は、子どもが1歳になるまでの期間に取得することができる養育のための休業で、こちらは男女ともに取得することができます。
| 名称 | 種類 | 対象者 | 期間 |
| 産休 | 産前休業 | 女性労働者 ※取得条件なし | 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得可能 |
| 産後休業 | 女性労働者 ※取得条件なし | 出産の翌日から8週間 ※産後6週間後、本人が請求し医師が認めた場合は就業できる | |
| 育休 (育児休暇) | 男女労働者 ※取得条件あり | 子どもが1歳になるまでの間で希望する期間 |
参考:厚生労働省・あなたも取れる!産休&育休https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf:公開終了
育休の取得要件
産休は全ての女性労働者に取得の権利がありますが、育休に関しては取得するために必要な要件があります。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
期間を定めない雇用契約の場合にはこの要件に関わらず取得できます。
また、雇用期間が1年未満や、1年以内に雇用期間が終了する場合、所定労働日数が2日以下の場合、そして日々雇用の人も取得できません。
育休制度を利用する場合には、要件に該当するかどうか事前に確認しておきましょう。
解決策②短時間勤務制度を使う

続いての解決策は、短時間勤務制度を利用する方法です。
短時間勤務制度(育児のための所定労働時間短縮の措置)は、
3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない(引用:「厚生労働省 育児・介護休業制度ガイドブック」https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf:公開終了)
というものです。
| 名称 | 対象者 | 労働時間 | 期間 |
| 短時間勤務制度 | 3歳に満たない子を養育する労働者 | 1日の所定労働時間を原則として6時間 | 原則、子どもが3歳に達するまで |
短時間勤務制度の適用条件
育休制度と同じように、時短制度にも適用条件があります。
入社1年未満の労働者や、週の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外とされています。
また、その期間も子どもが3歳に達するまでと定められています。
他にも、「育児・介護のための所定外労働の制限」(残業の免除)や、「育児・介護のための時間外労働の制限」といった制度もあります。
解決策③家族とのサポート体制をつくる
前出の2つの解決策は国や自治体が定めた制度で、雇用主の理解や協力が必要なものです。
その制度を利用するのか利用しないのかに関わらず、まずは家族の理解やサポートが必須です。
パートナーのサポート
もっとも身近で、最も理解やサポートが必須なのがパートナーです。
勤務時間の調整や、子どもの体調不良時にどちらが保育園のお迎えに行くのかといった対応を事前に話し合っておく必要があります。
また、家事の分担など家庭での役割も、復帰する前にしっかり話し合っておきましょう。
両親や兄弟のサポート
パートナーのサポートは不可欠ですが、パートナーがいない、パートナーの協力が難しい場合には、両親や兄弟などの家族にサポートしてもらうのもひとつの選択肢です。
保育園のお迎えや家事の一部をサポートしてもらうことで、いくらか負担の軽減になります。
解決策④転職して、より働きやすい職場に移る
どうしても今勤め先では子育てとの両立が難しいということであれば、思い切って転職してしまうのも一つの手です。
正社員としてより良い条件で働いたり、時間の融通が難しければパートや派遣として働いてもいいかもしれません。
ただどうしても昼までの時間帯の募集は少ないです。自分にあった条件の求人を根気よく探しましょう。
実際転職としたら、どんな働き方がある?
公務員保育士
待遇や給料など安定している職場に公立保育園があります。試験や年齢制限があるためあまり現実的な考えではないかもしれませんが、長期的に目を向ければ一つ選択肢になるかもしれません。
時短正社員
時短正社員を募集している園もあります。その保育園によって異なりますが、1日6時間ほどで正社員と変わらずに働くことができます。もちろん今までのキャリアを中断することなく働けます。
派遣保育士
派遣の保育士であれば、時給が比較的高い上に時短で働くこともできます。雇用が期限付き、ボーナスが出ないというデメリットはありますが、自分の希望に合わせた時間帯で働けるのは大きな魅力です。
パート保育士
パート・アルバイトとして保育園で働く方法もあります。フルタイムではないので担任を任せられることはないですし、自分の生活スタイルに合わせて働くことができます。時給は高くありませんが、勤務日数によっては有給休暇や雇用保険もあるので安心です。
両立のために、今からできること
子育てと仕事の両立を目指すのであれば、産休・育休制度や時短勤務制度を利用すれば助かるのは間違いありません。
しかし、そういったワーキングマザーにうれしい制度も勤務する保育園の理解が無ければ利用することができません。
出産まで勤務していた保育園で、育休・産休や時短制度を取り入れていない場合には、転職することも視野に入れて復帰計画を立てましょう。
保育専門の転職サイトや転職エージェントなら、ワーキングマザーのための制度が整った保育園や幼稚園の求人情報がたくさんあります。
保育専門エージェントを利用して、子育てと保育士のお仕事を上手に両立できる職場を見つけましょう!
❀ 保育のお仕事探しなら保育情報どっとこむ
❀ 保育関連の転職やキャリアなどの相談は保育士くらぶ相談室