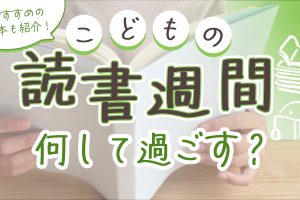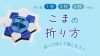子どもたちにとって大切な「遊び」。外遊びや室内遊び、道具の有無など様々ありますよね。保育士さんにとっては、準備や後片づけ、子どもたちの安全確認などしなければならないことも多く、日々大変かと思います。今回はそんな遊びの中でも、「道具を使わない外遊び」についてご紹介します。遊びの種類はもちろん、ねらいやメリット、ポイントについても紹介しているので是非チェックしてみてください!お悩みの保育士さん、新人保育士さん必見です!
道具を使わない外遊びのねらい・メリット
コミュニケーション能力の向上
道具を使わずに遊ぶため、一緒に遊ぶ人との会話が重要となってきます。保育士さんや友だちとルールを決めたりコミュニケーションを取りながら遊ぶ必要があります。そのため、普段おとなしい子どもでも言葉を発したり、互いに声掛けをしあったりなど自然に会話が生じる場と言えるでしょう。また、チームを組んだり協力し合ったりなど相手のことを考えて動けるようになるので、子どもたちの心の育成としても大きなメリットがあるのです。
体力作り
外遊びということで、走ったり逃げたりなど体を動かす遊びが中心となります。また、室内とは異なり日光を浴びたり寒さや暑さを感じることから、体を強くする機会でもありますね。加えて、道具を使わない遊びであれば、隠れる逃げるなどといった走る行為が多くなるので持久性の強化としても効果的です。このような遊びを定期的に取り入れることで、体力強化につながり運動する習慣も身に付くのです。また今は、感染症の流行や、真冬ということもあるので体力作りには欠かせない遊びと言えるでしょう。
思考力の向上
道具を使わない外遊びは、子どもたち自身がルールを決めたり守ったりなど考えながら遊ぶ必要があります。「どこに隠れれば捕まらないかな」「どうやって追いかけたら○○ちゃん/くんを捕まえられるかな」「順番は守らないと」「そこに行ったら危ないかも」など自然と考えることが多くなります。また、遊び方やルールを覚えること自体も子どもたちにとっては思考力・理解力向上に大きく繋がります。遊びに関して、友達が知らないことを教えてあげる子どももいるかもしれませんね。
感染防止に効果的
コロナウイルスを始めとし、多くの感染症が流行しやすい保育園。冬は特に流行する季節なので保育士さんも気を貼っていることかと思います。道具を使わない遊びであれば、子どもたちが道具を共有して触れることもないので消毒や管理の負担が軽減されます。また、外遊びという点でも、空気や広さの面で室内に比べて感染リスクを減らすことが出来ます。接触や密空間の心配もあまりないですよね。天気のいい日や寒すぎない気温の日は積極的に外遊びを取り入れましょう。
状況に応じて気軽に遊ぶことが出来る
道具を使わないということは、基本的に準備や後片づけが不要となります。そのため、状況に応じて臨機応変に対応できるメリットがあります。また、保育士さんの負担が軽減されるだけでなく、実施したいときに気軽に始めることが出来る点も魅力的と言えます。なるべく遊びのバリエーションを増やし、急な時に提案できるようにしておきましょう。晴れている、比較的暖かいなど天候の条件によって積極的に取り入れてみても良いでしょう。
【大人数編】みんなで楽しめる遊び
だるまさんがころんだ

【対象年齢:2歳~】誰もが経験したことのある定番の遊び。最近は、海外の某作品の人気で日本でも流行していますよね。対象年齢も比較的低いので、多くの子どもたちで一緒に遊ぶことが出来るという特徴があります。また、「だるまさんがころんだ」以外にもさまざまな言葉で言い換えることが出来るので、オリジナリティあふれる遊びにすることが出来ます。今回は大人数編での紹介ですが、2人~の少人数で遊んでも同様に楽占める遊びです。
しっぽとりゲーム

【対象年齢:2、3歳~】ズボンなど服にしっぽとなるひもやタオルを挟んで鬼に取られないように逃げるゲーム。しっぽにはハチマキや製作で使うリボンなどさまざまな物を使うことが出来ます。しっぽをめがけて追いかけるのでスリル感あふれる遊びです。また、実際には2,3歳の子どもたちにとっては難易度が高く難しいケースもあるかもしれません。保育士さんのサポートやルールを変えるなどとしどんな子どもも楽しく遊べるように工夫しましょう。
ポコペン

【対象年齢:5歳~】実はあまり知られていない遊び、ポコペン。小学生の子どもたちも遊ぶ楽しい遊びとして親しまれています。缶蹴りと似ていますが、ポコペンは道具が必要ないという点で魅力的と言えるでしょう。遊び方が少々難しいので対象年齢は高めですが、「ポコペン♪」と言いながらタッチをしたり走ったり、隠れたりなどするスリル感あふれる楽しい遊びです。複雑なルールでもあるので、あらかじめ全員が理解できるような説明をする必要がありますね。
かくれんぼ

【対象年齢:3、4歳~】子どもたちに大人気の遊び、かくれんぼ。鬼を決め、その他の人は捕まらないように隠れたり逃げたりするスリル満載の遊びです。今回は外遊びとして紹介していますが、室内でも遊ぶことができ、道具も必要ありません。人数に関しても大人数だけでなく少人数で楽しむことも出来ます。また、かくれんぼといってもさまざまな種類があるので、時と場合によってルールや範囲を変えてみると楽しいかもしれません。
オオカミさん今何時?

【対象年齢:3歳~】「だるまさんがころんだ」と「鬼ごっこ」を混ぜたような遊びとして知られていますね。鬼とその他に分かれて、「オオカミさん今何時?」「○○時」というやり取りをします。この時点ではだるまさんがころんだのように、鬼以外の人が9時なら9歩、鬼に向かって進みます。繰り返す中で、鬼が「夜中の12時!」と言ったら鬼ごっこがスタート。オオカミにつかまらずに逃げ切ることが出来れば成功ですが、捕まれば鬼を交代します。オオカミではなく、他の動物に変えて見たりルールに変化をつけてもいいかもしれません。
はないちもんめ

【対象年齢:4歳~】伝承遊びとしても知られるはないちもんめ。大人数でやるからこそ楽しい遊びですよね。2つのグループに分かれ、わらべ歌を歌いながらみんなで手をつないで勝負することが特徴です。「あの子が欲しい」「相談しよう」「そうしよう」などと歌い、じゃんけんで決める過程はとてもハラハラしますよね。基本的にはどちらかのグループが全員呼んだら終了となりますが、時間で区切ったり特別なルールを設けてみても楽しいかもしれません。
【少人数編】1人や2人~楽しめる遊び
けんけんぱ
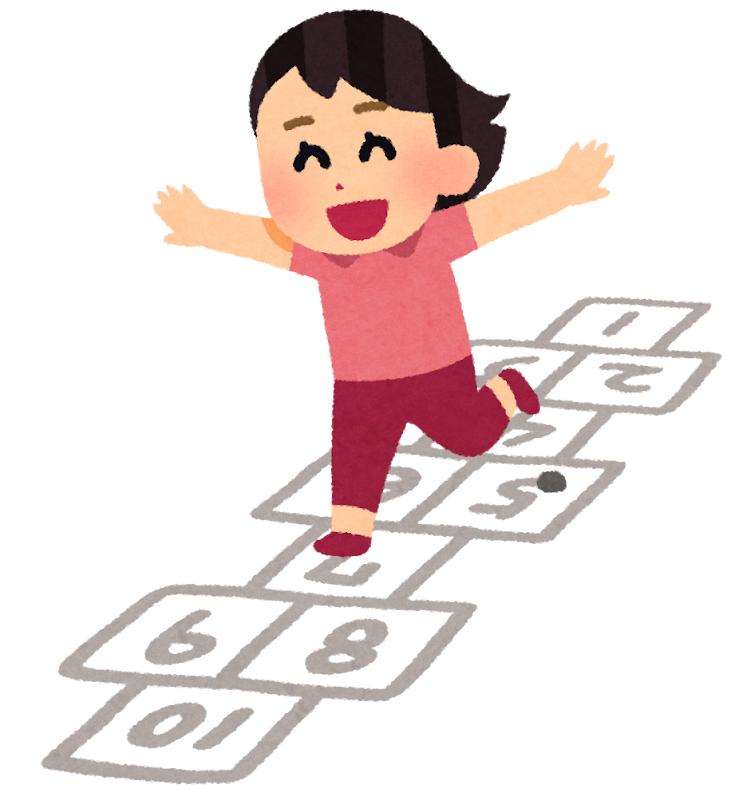
【対象年齢:3歳~】昔ながらの遊びとして親しまれているこの遊び。「けんけんぱ」という掛け声が特徴的ですよね。丸いわっかを置いて遊ぶ方法もありますが、木の枝や落ち葉を使って丸を作ることもでき、道具を使わなくても楽しむことが出来るのです。対象年齢は3歳~ですが、片足跳びが難しい場合は両足跳びやゆっくり飛ぶことを促しましょう。また、バランスを崩しやすい遊びなので、大人である保育士さんが1人1人きちんと見守ることが大切です。
○○探しゲーム

【対象年齢:2,3歳~】一般的には宝探しゲームと呼ばれることが多いですよね。今回は、外かつ道具を使わない遊びということで、「自然探し」「お花探し」など自然をテーマとした遊び方の紹介です。お題を決め、それらを子どもたちが探すという定番かつ単純な遊び。隠したものではなく、自然にあるモノなので子どもたちの感覚を養うことが出来ます。一方、花や枝など自然の草花をむしり取ることがないように注意を促すことも大切と言えるでしょう。毎回お題を変えて実践してみると良いですね。
影踏み鬼
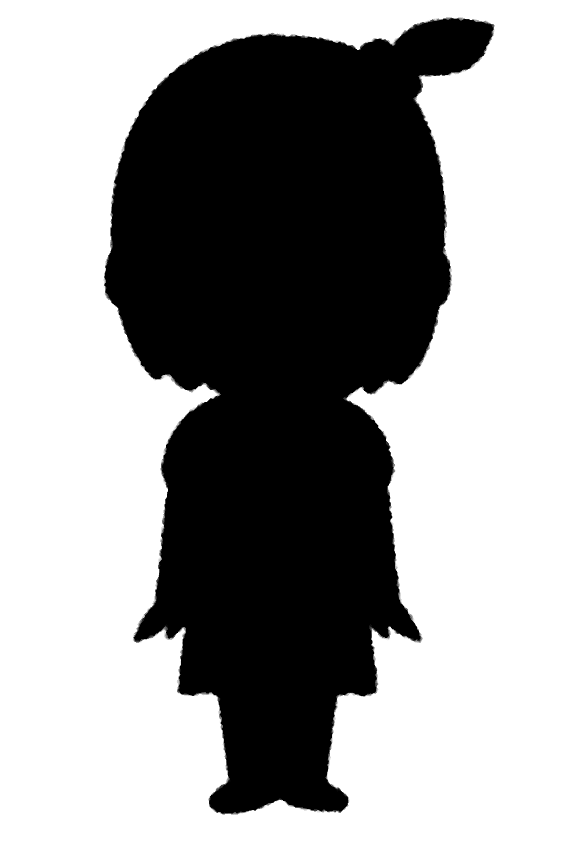
【対象年齢:2歳~】この遊びのポイントは、天気が良く影が出ている時でしか行えないことです。実際の影を踏むことで成り立つため、遊びをする際は影が出ているかをきちんと確認しましょう。鬼に影を踏まれたら負けとなってしまうため、自分の影を踏まれないよう移動したりなど考えることが重要となります。実際に遊べていても、途中で雲の動きにより影がなくなることもあるので適度に鬼と逃げる側で交代しながら遊ぶとよいでしょう。
忍者ごっこ

【対象年齢:2歳~】道具を使わない遊びということで、忍び足や手を使って手裏剣を投げる真似をします。忍び足や手裏剣にもさまざまな種類があるので、保育士さんや子どもたち同士で技を提案し合ってみると楽しいかもしれません。手足を動かす動作が多いので、子どもたちの運動にもなります。また、向かい合って遊んだり、保育士さんの指示で動いたりなど遊び方も自由なので、少人数で遊べるメリットがあります。天気が悪い日は室内でも遊ぶことが出来ますね。
じゃんけんグリコ
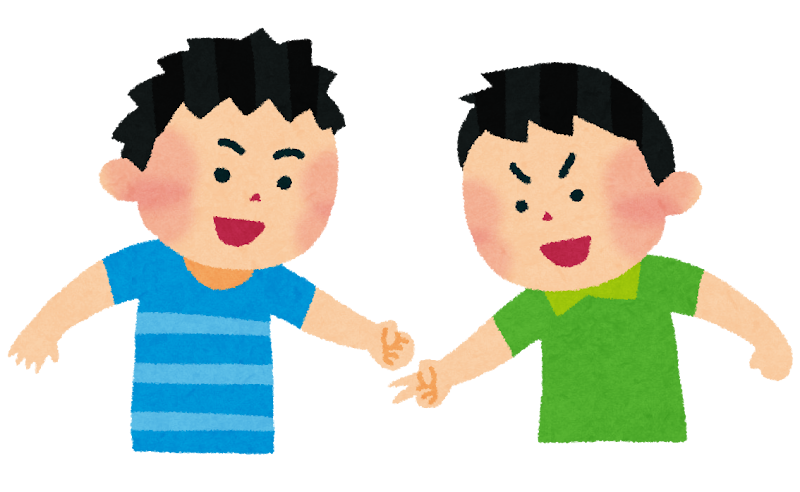
【対象年齢:4、5歳~】じゃんけん遊びで有名なグリコ。グーを出したら「グリコ」、チョキを出したら「チョコレート」、パーを出したら「パイナップル」というようにその字の数だけ前に進みます。階段など凹凸のある個所で遊ぶと分かりやすくて楽しみやすいかもしれません。声に出しながら進むようにしましょう。先にゴールできた人が勝ちです。ゴール場所を決めたり、グリコやチョコレート、パイナップル以外の言葉にしてみるなどアレンジしてみると良いですね。
あんたがどこさ

【対象年齢:2歳~】お手玉を使って遊ぶ方法が知られていますが、今回は地面に輪を描いて遊ぶ場合の紹介です。円を4つ描き、わらべうたである「あんたがどこさ♪」のリズムでジャンプをし、移動します。全身を使うので子どもたちにとって運動にもなりますね。1人でも遊ぶことは出来ますが、数人で一緒に歌ったり、友だちと交代しながら遊ぶとより楽しめます。歌詞をアレンジしたり動くスピードを早めるなど工夫することでより盛り上がるでしょう。
道具を使わない外遊びのポイント
自然を取り入れる
外遊びかつ、道具を使わない遊びは自然を取り入れるチャンスです。自然と触れ合うことは、子どもの視覚、聴覚、嗅覚などさまざまな感覚を養うきっかけとなりとても大切です。時には命の大切さに触れることもあるでしょう。感受性や想像力も働き、子どもの成長に絶大な効果があります。特に現代では、自然と触れ合う機会が減少し室内で過ごすことも多いことから、幼少期に遊びの中で触れあうことはとても重要と言えます。
年齢に沿った遊びをする
年齢やレベルに沿っていない遊びをすると、子どもたちの成長を感じられない他、子どもたち自身が楽しむことが出来ないというデメリットが強くなります。特に、実際の年齢よりも対象年齢が上の遊びをしてしまうと、子どもたちが難しいと感じたり「自分はなんで出来ないんだろう」と自信を失ってしまいます。年齢だけでなく、子どもたちそれぞれに個人差もあるのでレベルを見極めることも重要です。日頃から子どもたちの様子を観察することが大切ですね。
ルールを決める
遊びにルールや決まりを設けることはとても大切です。ルールを決めていないと、線引きがわからなくなり子ども同士の喧嘩や怪我が生じやすくなってしまいます。一方、ルールを守らなかったり破ってしまったら、した側を負けにしたり終わりにすることで、子どもたちが守るようになります。遊ぶ前に、子どもたちに説明したり見本を見せるなどし、共通認識にしておくことで誰もが気持ちよく遊べるよう心がけましょう。
怪我に注意する
外遊びは常に危険が伴います。遊ぶ際に、走ったり逃げたりすることで転んでしまうと怪我をする機会は増えてしまいます。また、外は範囲が広いこともあり、目を離したすきに遠くへ行ってしまう子どもも少なくありません。遊具や自然の物で怪我をしてしまう可能性もあります。子どもたちの体調管理もきちんとしておく必要があります。どんな時も子どもたちが安心安全に遊べるように、事前に遊ぶ範囲や時間、約束事をきちんと決め、常に見守るようにしましょう。
まとめ
道具を使わない外遊びも積極的に取り入れよう
いかがでしたでしょうか。今回は、道具を使わない外遊びを多く紹介しました。準備や後片づけに手間がかからない他、いつでも気軽に始めることが出来る点から、是非とも取り入れたい遊びですよね。また、想像以上に多くの遊びがあることを知ることが出来たのではないでしょうか。道具を使わない外遊びを積極的に取り入れ、どんな時でも楽しめるようにしましょう!
ここで新人保育士の物語を描いたマンガを紹介します!保育士であれば誰でも共感できること間違いなしです!是非チェックしてみてください♪
よくある質問
保育士くらぶにはどんな記事がありますか?
保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。
保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?
最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。
保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?
保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。