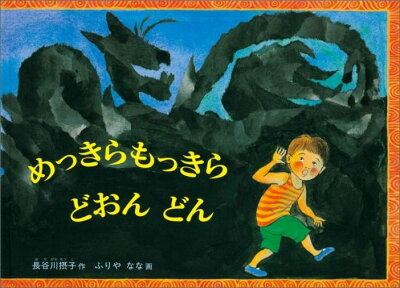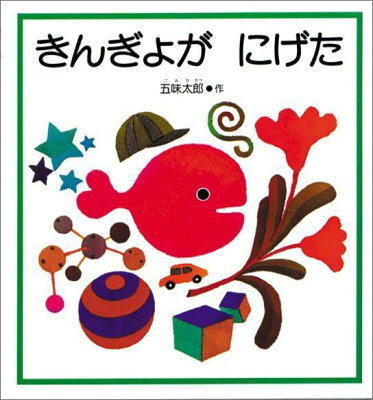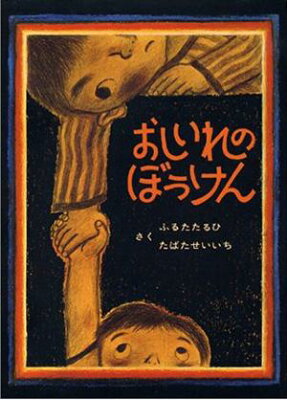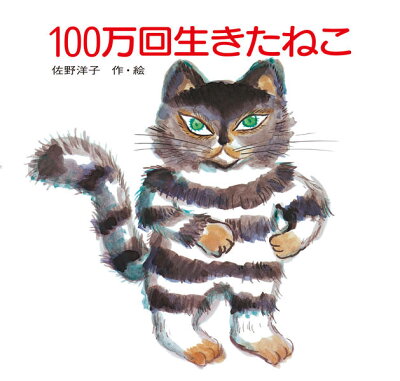目次
子どもは絵本の読み聞かせが大好きです。
そこには、自分で読むのではなく読み聞かせてもらうことの幸福感もあります。先生の表情がころころと変わるのを見るのも、子どもたちにとっては楽しいものなのです。子どもたちは、保育士さんに絵本を読んでもらうそんな時間を心待ちにしています。
今回は読み聞かせにいい絵本の選び方や読み方のコツをご紹介していきます。
絵本の読み聞かせをするとどんな良いことがあるの?

読み聞かせの持つ、いろんな効果
絵本の読み聞かせにはいろいろな効果があると言われています。
まず、想像力や好奇心を育てます。「この先はどうなるんだろう?」物語に引き込まれた子ども達は、絵本の中の世界に思いを寄せていきます。
また、言語能力や語彙力が豊かになります。子どもは、最初は文字ではなく「耳から」言葉を吸収していきます。読み聞かせることによって、様々な言葉に触れ自然と覚えていきます。
さらに、集中力も付くうえ、感情を豊かにする効果もあるそうです。絵本の読み聞かせには、シンプルながら様々な効果があるのです。
『クシュラの奇跡』-絵本による言語機能の発達効果を示す実例
絵本による言語機能発達を象徴する実例として、「クシュラの奇跡」という本があります。
1971年にニュージーランドで生まれたクシュラは、先天的に重い障害を抱えていて精神・身体の発達に遅れがありました。
しかし、生後4か月から毎日絵本を読み聞かせたことで、知能や身体的機能が驚異的な発達を見せ、成長していきました。
もちろん科学的・医学的に根拠があることではないので「奇跡」と呼ばれています。クシュラに起こったことは特異な例ですが、読み聞かせが子どもの情緒や想像力の発達に効果があるのは良く知られています。
【0~1歳児】オススメの絵本・絵本の選び方
まだ言葉を覚えていない0歳〜1歳の乳児さんに絵本の読み聞かせを行う場合には、視覚的な部分に重点の置かれた絵本がいいでしょう。
カラフルな色使い、インパクトのある絵といったことや、擬音や簡単な言葉を使った絵本を選ぶといいでしょう。
もこもこもこ
- 作 谷川 俊太郎/絵 元永 定正
「しーん」「もこもこ」「にょきにょき」と擬音語ばかりで織りなす絵本。最後にふくれあがったものが「ぱち」と弾けると子供達も喜びます。不思議でおかしな絵本です。
わんわん わんわん
- 作/絵 高畠 純
いぬ・ねこ・ぶたなどの動物の鳴き声が楽しい絵本です。
可愛くてわかりやすいビジュアルで、はじめての読み聞かせにおすすめの絵本です。
いっしょにあそぼ しましまぐるぐる
- 作/絵 かしわら あきお
「いっしょにあそぼ」シリーズの0歳〜1歳の乳児さん向けの絵本です。
カラフルなしましまやぐるぐるが、赤ちゃんの視線をとらえて離しません。
【2~4歳児】オススメの絵本・絵本の選び方
言葉が分かり始めていろんなものに興味が広がる1〜2歳の子どもには、これはなあに?と問いかけたりして言葉のキャッチボールができる絵本などがおすすめです。
3〜4歳になると、登場人物に自分を重ねて参加し始めたりします。感情移入しやすい絵本で子どもたちを巻き込んで読み聞かせましょう。
ねないこだれだ
- 作/絵 せな けいこ
こんな時間に起きてる子だれだ?ここからはおばけの時間だよ。子供の寝かしつけに最適の絵本。
おおきなかぶ
- 作 A・トルストイ/絵 佐藤 忠良
「うんとこしょ どっこいしょ」でおなじみのロングセラー絵本です。
かぶをみんなで抜く動作をすると盛り上がりそうです。
めっきらもっきら どおんどん
- 作 長谷川 摂子/絵 ふりや なな
どきどきハラハラの冒険物語です。途中で出てくる「めっきらもっきら どおんどん」のお歌も楽しいです。
きんぎょが にげた
- 作 五味太郎
金魚が金魚鉢からにげちゃった!さてどこにいるかな〜?絵探しのロングセラーの本です。
【5~6歳児】オススメの絵本・絵本の選び方
理解力や語彙力も上がり、多少複雑な物語も分かるようになってきた5〜6歳の子どもには、考えさせる物語や新しい発見のある絵本を選びましょう。
おしいれのぼうけん
- 作 ふるた たるひ、たばた せいいち
押入れの中で遭遇した「ねずみばあさん」のインパクトや、ドキドキハラハラする絵本の展開は印象的で幼いころ読んだことを覚えている人もいるのではないでしょうか。
物語を理解する力を深めるのにピッタリの絵本です。
100万回生きたねこ
- 作/絵 佐野 洋子
笑って泣いて…大人も楽しめる深いお話です。
読み聞かせるときは、猫の徐々に変化していく感情をわかりやすく表現しましょう。
キャベツが食べたいのです
- 作 シゲタサヤカ
「花のミツなんて甘いだけ。やっぱりあの味が忘れられない!」
青虫の時のなつかしい味を求めて5匹のチョウチョたちが辿りついたのは、一軒の八百屋さん。はたして、彼らの願いはかなうのでしょうか?!
絵本の読み方のコツ
園児にわかりやすく絵本の内容を伝えたり、集中してもらうためには読み方のコツが必要です。
0〜1歳の絵本の読み方のコツ
まだ言語機能の発達が十分ではない乳幼児には、擬音や簡単な言葉を中心に聞かせるように読み聞かせしましょう。
また、大きなジェスチャーなどで注意を引き、子どもたちとコミュニケーションを取りながら読み聞かせると効果的です。
2〜4歳の絵本の読み方のコツ
1〜2歳は言葉を理解し始める時期です。
言葉の意味や簡単な物語なら理解できるので、絵本の流れにあわせて抑揚をつけて読み聞かせすると良いでしょう。
3〜4歳の子どもはさらに言語機能の発達が進み、物語への感情移入ができるようになります。
絵本の物語に集中できるように、抑揚をつけたり声の大小をつけたりすると良いですね。
5〜6歳の絵本の読み方のコツ
この時期になると、多少難しい言葉や物語を理解できるようになります。
飽きてしまう子もいますから、どれだけ話に引き付けるかが保育士さんの腕の見せ所です。
登場人物ごとに声色を変えたり、表情をつくったり、時には集中しないと聞こえないくらいの小さい声にしたりといったテクニックを使って、読み聞かせると読み聞かせを楽しんでもらえます。

【おまけ】絵本のプロフェッショナル、絵本専門士とは?

日常の読み聞かせだけでは満足できない!どうせなら絵本のスキルを極めたい!もしそう思う保育士さんがいれば、こんな資格があります。
それが、読み聞かせのプロともいえる「絵本専門士」という資格です。
読み聞かせのスキルや、子どもの成長に合わせた絵本の選定といった、絵本に関する高度な知識や技能を備えた絵本のスペシャリストです。
「独立行政法人 国立青少年教育振興機構」が平成26年に開設した養成講座を修了することで認定される民間資格ですが、難易度の高いこの資格取得者はまだ全国で160名ほどです。
平成31年度からは、大学や短大などで「認定絵本士」養成講座がスタートします。
この認定絵本士として実践経験を積めば、「絵本専門士」への道が開けます。
お仕事で絵本の読み聞かせをすることが多い保育士さんにとって、非常に有意義な資格です。
みんな大好き絵本の時間。ちょっとしたした工夫でもっと楽しくしましょう。
絵本の読み聞かせについての記事、いかがでしたでしょうか?
子どもたちが大好きな絵本の読み聞かせ。保育士さんのちょっとしたテクニックやスキルで、もっともっと子どもたちはワクワクどきどきすること間違いなしです!