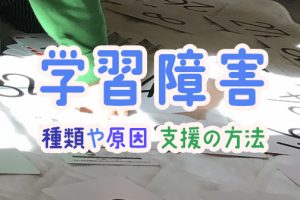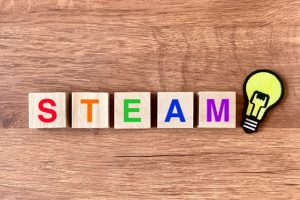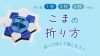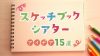目次
こんにちは!今回は離島で働く現役の保育士さんにインタビューさせていただきました。
離島ならではの保育のお話をお聞きしました。
インタビューの舞台は
そこは福岡市西区。
穏やかな海に包まれるように、小さな離島「玄界島」は存在している。

福岡市内からバスやフェリーを使って30分弱。
別世界のような雄大な自然と静寂。
漁業者の活気や地域住民同士の会話。
どれも都会での生活では触れることのできないものたちだ。
島唯一の保育園、「玄界島保育園」には今日も子どもたちが元気に登園してくる。
先生たちに迎えられ、元気な挨拶とともに1日が始まる。
昭和55年の発足以来、現在は14名の園児を受け入れている。

島に生まれ、島で育つ。
島を想い、島で働く。
そこには、保育士や地域の住民、保護者や子どもたち、
それぞれが離島の生活に寄り添う温かな保育のあり方があった。
シンプルに、健康的に。大切なことを育んでいく~
松田ゆかり園長先生~
「挨拶をすること。靴をそろえること。人の前を歩かないこと。心を込めて話を聞くこと。
人生で必要な、基本的なことを子どもたちには教えたいのです」
そう話してくれたのは、当保育園発足時から保育士として勤務を始め
40年弱に及び島の子どもたちを見守ってきた松田ゆかり園長。
インタビューに応えてくれる表情には、随所に温かさがにじみ出ている。

「ここは漁師町ということもあり、みんな気が短く気性が荒いんです。話をしていても言い合いになったりワッとなることがある(笑)そういった地域性から、園ではまず話を聞ける子を育てようと思いました。朝体を動かした後に私や保育士さんたちの話を聞いてもらう時間を作っています。」
そして松田園長はこう続ける。
「ただじっと座っていることがゴールではないんです。大切なのは心技体。心を傾けて話を聞き、目できちんと話し手を見る。その人がどんな気持ちで話をしているのかを想像する。そうして心の通ったコミュニケーションを覚えていくんです。」
先生たちは子どもたちの意見も聞く。
どう思うか、どう感じたか。
自分なりに言葉にする。
そうすることで、年齢は関係なくきちんと話の聞ける子どもが育つのだそう。
「朝のうちに運動をしてしっかりと体を覚醒させる。集中力が増すのでまずは運動です。毎日続けることで、早い子では3歳で登り棒や連続逆上がりができちゃうんですよ。子どもたちの運動能力は本当にすごい!と自信をもって言い切れます(笑)」

こうして玄界島の子どもたちの“心技体”は育まれていく。
ただ一方で、子どもたちの成長に離島ならではの課題があるのも事実だと教えてくれた。
多様な考え方に触れる。自分の意思を発信する。その力をどう伸ばすか
離島では人間関係の幅が狭いがゆえ、
子どもたちには考え方の多様性に欠ける部分や、
自分の意思を発信する力が弱いと感じる面もある。
小学校や中学校に上がっても人間関係に変化がないため、
小さいころからの性格や気質が変わらなく、
成長の幅にリミットができてしまう可能性もあるのだという。
「ダンスや空手、ピアノやサッカーなど、モノやコトへの“欲”もおそらく都市部の子どもたちに比べては少ないと思います。できるだけ多くのチャレンジや興味の場を持てるように私たちが積極的に仕掛けないといけないと思っています」

以前外部から講師を招いて英語や楽器に取り組むことへも挑戦したが、
費用や時間の面で継続させるには困難なことが多かった。
保育方針についての園側の課題も同様だ。
「現在園の定員は14名。人数が少ないので教育方針が育ちにくいんです。自分たちが思い描く保育のあり方や目指す姿、それが本当に子どもたちに合っているのか、時間をかけてより良いものに昇華していけるのかという点に関してはやはりまだ弱い部分があります」
少人数の密接したコミュニティだからこそ、1人1人に寄り添った保育ができるのは事実。
離島ならではのいい面も捉えたうえで、課題をどうフォローしていくかが今問われている。
心を満たす“おすそ分け”。垣根を超えた共生のカタチ
園にはフェリーで通勤している保育士も。
天候などで帰宅できない時のために、園の一室をスタッフ専用の部屋として確保している。
風呂も自由に使え、食事は近くの農家や漁業の方が差し入れをもってきてくれる。
人と人との結びつきがもたらす地域のあり方はきっと他では見られないだろう。

運動会には近所のおじいちゃんおばあちゃんが、まるで自分の孫を見に来るかのように応援に来る。
親や先生以外の大人からほめてもらうという体験は子どもの成長にはとても大事、と松田園長は言う。
そんな地域の絆を松田園長は「心が満たされる」と表現する。
ここにはコンビニもファストフード店もない。
お金を払えば楽にご飯が食べられる時代に、
自分たちの手で、自分たちの土地を活かして作った食材を食べることや地域の大人との関わりは
まさに、お腹以上に心を満たす要素になっているに違いない。
島の子どもたちにとって玄界島保育園は、
「島の保育園」として生まれたときから馴染みがある。
そのため、ここでは慣らし保育の制度は取り入れていない。
どの子もみな緊張しながらも、入園と同時にすぐ園での生活に親しめるのだという。
それくらい島の住民にとって唯一の保育園の存在は大きいのだろう。
この島をふるさとに。地域全体で子どもたちを育てていく
「島の仕事は少なく定着率が低い、人口が増えない、子どもが増えない…と
少子高齢化の影響は痛いほど感じる。」と松田園長は語る。
「例えば最近目にする虐待のニュース。事情によって家庭での子育てが困難になった子どもたちの行き場が少ないように感じます。そういった子どもたちを島で受入れ、島の住民で育て、うちの保育園へ通ってもらい、ここをふるさとにして住み続けてもらえたら…」

自分や社会が抱える課題に対し、何かしないと、と思っていても、
なかなか行動として表に出るまでには時間が必要だ。
島全体で社会貢献できる仕組みを作ることに今後は取り組んでいきたいと、松田園長の志は強い。
“今すぐ”より、“長い目”で。人の成長を見守り続ける
「若いときは使命感に駆られて、私が何とかしなきゃ、とか今すぐ何とかしなきゃ、と憤っていたけれど(笑)」の前置きとともに、松田園長は最後に、保育にかかわる人に向けメッセージを伝えてくれた。
難しいことはしなくていい。
良い悪いの基本をしっかり教える。
人としていけないことはきちんと伝える。
「ゆっくりでいい。すぐに何かをするのではなく、長い目で子どもたちを育てていく。」
それは、園に通う3年や5年というスパンではなく、
この園から巣立ち、義務教育を終え、
この島で働く何人もの人を見守ってきた松田園長ならではの言葉だろう。
「悩んだときは遠慮せず先輩に頼って、
現役の保育士さんに少しでも長くこの業界に携わってほしいと願います。」
大先輩のようなまなざしで松田園長はそう締めくくった。
180度異なる環境。それがすべてのきっかけに~
加納先生 ~
玄界島保育園で勤務する前は、今よりも園児数の多い120名ほどの園で勤務していたという加納先生。
以前玄界島で働いていた友人に誘われ、島での合同運動会を見に来たことがきっかけだった。
「1クラスにも満たない環境で、子どもたちとこれほどまでに密に関われる保育のあり方に感銘を受けたんです」
当時は保育士の募集はしていなかったものの、次の年に臨時職員の募集で声をかけてもらった。
そうして働き始めた玄界島保育園は、以前の園とは180度異なる環境だったという。

「以前と大きく違ったのは自由保育の部分です。例えば鉄棒をするにしても、ここでは子どもたちに“やらせる”という感覚はない。その子が『やりたい』『やってみたい』という気持ちで自ら取り組むまで僕たちは気長に待ちます。」
子どもたち一人ひとりのペースに合わせた保育がしたい。
保育士がそのような想いを口にすることは少なくないが、
大勢いる園児たちを前にそれがどれほど難しいことかは周知の事実だ。
「以前の園だったら、好きなことを好きなだけ極めればいい、というやり方に対し協調性を保つのに今後苦労するのでは、という保護者からの声もあった。それも確かに理解できます。園児が多いとその同じ数だけ保護者もいますから、さまざまな要望や意見がくる。すべての要求に応えたくても実現するのはとてもハードルが高かったんです」
その点、ここ玄界島保育園では、言葉通り“1人1人のペースで”、好きなことに全力で取り組む姿勢をバックアップしている。
しかし、ただ成り行きに任せて自由にさせるのではなく、きちんとしたけじめを持つことが重要なのだということも教えてくれた。
人は人を見て育つ。だから私たちも努力を欠かさない
「うちの保育園では年中以上の子は全員すでに逆上がりができます。年少の子は上の子を見て、負けまいと必死に毎日練習しています(笑)」
兄弟でもそうであるように、下の子は上の子を見てたくさんのことを吸収していく。
それは子ども同士に限ったことではない。
子どもは周りの大人を見て同じように、行動や姿勢を習得していく。
「職員同士でも、逆上がりをどのように教えようかと真剣に議論をします。室内用の鉄棒を購入したり、その子の状況に合わせて園長先生からも、こんなことに次は力を入れてみたら?など僕たち自身が挑戦する機会をアドバイスいただきます。」

数少ない職員に対しての研修も充実している。
「けじめをつけることが大事です。気持ちが入った時だけ好きなだけやる、というのは違う。やりたいと思ったら、どうやったらそれを成し遂げられるか、苦手なものをどう克服していくかを考え、きちんと継続して頑張り続けること。きちんと努力をすること。それは僕ら保育士がまず姿勢として見せなければならないと思っています」
保育園で培ったその力は、今後子どもたちにどう活きてくるか。
彼らの成長がつい楽しみになるような指導がそこにはあった。
人数が少ないからこそ「集団力」を。自分たちで解決する、ということ
現在の園児数は14名。
人数が少なく、集団力が身に付きにくいという側面もある。
「なるべく子どもたち自身で話し合って問題は解決させ、人との“関係性を築く”という力を養っています」
保育士たちは見守り、必要であれば助言をする。
「年中さん同士でトラブルがあれば、自然と彼らは年長さんに相談したりもします」
上下の意識を持ちながらも、年齢に関係なく他人と関われる環境が作られている。
それは園児同士だけでなく、保育士と園児の関係も同様なのだとか。

「子どもたちが先生にお手紙を書いてくれたりしたとき、人数が多いと全員にお返事が書けなかったり。今はそういったこともできるようになって嬉しいです」
16年フェリー通勤を続けている加納先生
悪天候で欠航になっても、園の管理室に寝泊まりができるので働く環境としては申し分ない。
これからもここで子どもたちと一緒にチャレンジを続けたいと、笑顔で締めくくってくれた。
勇気を出した1本の電話。新卒で単身離島へ~
深町先生 ~
「就活をしている時、主任のお話を聞いてこの保育園に惹かれたんです」
そう話すのは、勤務2年目の深町先生。
新卒で玄界島保育園へ就職を決め、単身親元を離れてこの島に渡ってきた。

「この保育園の保育のあり方に感銘を受けて、勇気を出して電話をし、まずは実習させてもらえないかお願いをしました」
実際に勤務し始めてからは、案外すんなりと島の生活に馴染んだ。
「もともと福岡出身ですが、ここでは島全体の住民が挨拶を交わしたり差し入れをしあったり…そういう光景は地元ではなかなか見られなかったので新鮮です。」
大変なことは、スーパーが17時半には閉まってしまうことと、買い物に行きたい日に限ってフェリーが欠航になることだという。
そんなところまで、島ならではです!と笑みを浮かべた。
先生から子どもたちへ。言葉のもつパワーの大きさ
「言葉一つで子どもの行動って変わってくるので、その子の状況に応じてどういった言葉を掛けたらいいかは日々意識しています」
今は小さい子のクラスを担当している深町先生。
年齢が低いほど短期間での心身の成長は著しい。
就職が決まった時に再度保育の現場を俯瞰してみて、これからどんな保育をしていこうか真剣に考えた。
「一人ひとり成長スピードは違うので、どうしたらその子に合った言葉をかけて行動を促せるかを模索しています」

自身もまだ保育士としては駆け出しの段階。
「私自身、もう少し心に余裕をもって保育に取り組まなきゃいけないなと日々反省もしています(笑)まずはそこからですが、今後は歌や踊りなど、私の力が活かせる部分で少しずつ島の保育に貢献していきたいです。」
小中学校ではエアロビクス、高校では和太鼓に取り組んできた。
短大時代にはエアロビでインカレ出場も果たしたという。
「今までにない環境で、他では経験できないことを経験できているありがたみを感じます」
親元や周りの友人と離れ、実は初めてホームシックも経験したという深町先生は、
先輩や子どもたち、島の住民からたくさんのことを吸収し、今日もまた奮闘している。
取材協力

玄界島保育園(社会福祉法人玄界福祉会)
福岡市西区大字玄界島1262番地
交通アクセス:ベイサイドプレイス博多埠頭 市営渡船 玄界島行き 停留所より徒歩5分
定員:20名
障がい児保育/一時保育/園庭開放 対応可

松田ゆかり園長 昭和55年、玄界島保育園発足時より当保育園で保育士として勤務開始 自身の子育てや地震でのブランクがありながらも園を支え続ける 主任を経て、平成10年より園長へ就任。今年で勤続38年を迎える

加納孝郎主任保育士 当保育園で勤務 保育士を経て主任へ就任 今年で当保育園勤続16年目を迎える

深町舞先生 福岡市出身 短大卒業後、新卒で当保育園で勤務を開始 今年で2年目を迎える