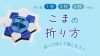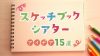泥んこ遊びとは、泥の感触に触れて泥で色々な物を作ったりする遊びです。泥んこ遊びは、運動能力の向上や社会性や協調性が身についたりと子どもに様々な効果をもたらします。泥んこ遊びのアイディアや注意点を理解することで導入がスムーズにいくかもしれませんね。色んな遊び方を知ることで泥んこ遊びの幅が広がりますよ。今回は、保育でできる泥んこ遊びの効果やタイミング、アイディア、注意点をまとめてみました!
泥んこ遊びがもたらす効果とは

感覚を育てる
形を自由自在に変えて遊ぶ泥んこ遊び。子どもはまず泥の見た目に対して興味を持たせ、泥のぬめぬめした感触や泥が水に濡れたドロドロ感など色んな泥の違いを実際に触りながら子ども達は楽しみます。遊びの中で、感触の変化を楽しむ事ができるのです。感覚が鍛えられて手先も器用になっていきます。また、泥に触って大脳を刺激してあげることで子どもの五感も養うことができるでしょう。
運動の能力の向上
泥の上を歩いたり座ったりする動きを繰り返すので、泥で遊ぶことで必然と運動量が上がります。また泥の上で深い穴を掘ったり、バケツの水を運んだりしてバランス感覚が身に付き運動能力の向上につながります。また。身体を動かして遊ぶことで子どもの情緒が安定することも期待できますね。泥の中で歩くだけでも運動不足の解消につながりますよ。決して無理をせず、子どものペースにあった泥んこ遊びを行いましょう。
社会性や協調力が身につく
泥んこ遊びで道具を使う時は一緒に遊ぶお友達と道具の貸し借りのルールを守り、楽しく遊ぶことが求められます。小さい子たちは、遊びの中でもお友達とのトラブルがつきものです。中には道具を貸してあげられなかったり、お友達が作ったものをわざと壊してしまう子もいるでしょう。そんなトラブルを自分たちで解決できるようになるとコミュニケーション能力が育ち社会性や協調力が身に付きます。また、子どもの協調性が育つとやっていいことと悪いことの善悪も理解することができますね。
失敗をしてもやり抜く力を身につけられる
子どもは失敗の中からさまざまなことを学びます。泥んこ遊びの中でも、失敗して製作物が崩れてしまうといったこともあるでしょう。子どもは、その失敗からどうしたら次は失敗しないだろうと考えます。そして、最後まで製作物を作りあげたときに子どもは達成感や失敗してもやり抜く力を身につけるのです。子どもがやり抜く力を遊びの中で自然と身につけることで、日常でも諦めずにやり抜くことができるかもしれませんね。
集中力が上がる
集中力とは一つの物事に集中して取り組むできることができる力のこと。泥んこ遊びに夢中になることで、遊びながら自然と集中力を高めることができます。集中力が上手く持続できるようになると作業が捗るペースや質に大きく繋がったり、色んなことが成功しやすいといった嬉しいメリットも。しかし、集中力というものは一般的にはそこまで続かないものです。無理に集中させず、適度に休憩しながら遊びに参加できるといいですね。
想像力を育む
想像力とは、自分の身は自分で守るためにできた力なのです。想像力は生きる上で大切なもの。泥んこ遊びでは、道具を使ったごっこ遊びやお城を作るときなど想像を膨らませて遊んだり、物を作る時がある思います。そういった遊びの中で、自然と想像力を身につけることができるのです。また、想像力が豊かだと大人でも驚くような発想で泥を使って色んなものを作り始めるかもしれませんね。
泥んこ遊びをするタイミング
口に入れておしゃぶりをしなくなったとき

0歳児の子達はなんでも口に入れておしゃぶりしてしまう子が多いです。0歳児の子はまず口にいれて安全かどうかを確かめる習性があるため、どんなものでもおしゃぶりをしてしまうのです。そのため、泥で遊ぶときに泥や使っている道具を舐めてしまう危険性があるかもしれません。泥には口に入れると危険なものが含まれていることもあります。そのため、口に入れておしゃぶりをしなくなった頃に始めるのが安心に遊べるタイミングと言えます。
泥んこ遊びのアイデア
泥団子作り

泥んこ遊びでまず思い浮かべるのは、泥を丸めて団子を作ることではないでしょうか。泥団子作りは泥んこ遊びの代表的な遊び。お友達や保育士さんとどちらが綺麗に作れたかを競っても楽しいと思います。泥団子のコツは、サラサラで乾いた砂を用意することでよりきれいに作ることができます。最近の泥団子はキットを用意することでピカピカの団子を作ることもできますよ。
ままごと
ままごとあそびとは、家族による日常生活を模倣した遊び。炊事や食事・洗濯といった日常で行われる家事の様子が模倣されることが多いです。ままごとあそびは一般的に室内でキッチンセットを使って行うイメージですよね。泥んこ遊びでも泥を使ってままごとをすることができるのです。ままごと遊びはどんなふうに喋ったらなりきれるのか、これはどんな動きをするのだろうと考える必要性があります。いろいろな人や物になるために考えることで、遊びながら想像力や発想が鍛えられるでしょう。
◯◯探しゲーム
◯◯探しゲームは、お題を決めてそれらを子どもたちが探すという定番かつ単純な遊びです。子どもたちはキラキラしたものなどお宝を探すのが大好きです!泥の中にビーズやボールなどを埋めて◯◯探しゲームをしてみるのはいかがですか。毎回お題を変えたり、はずれや当たりなどを決めておくことで更にゲームが盛り上がることでしょう。また、ビーズやボールなどはサイズが小さいため子ども達が誤飲しないように取り扱いには注意が必要です。
道具を使って遊ぶ

子どもたちのアイディアは無限大です。ケーキ型のカップケーキを作ってみたり、コップを持って乾杯してパーティーごっこをしてみたり…と道具を使った楽しみ方は様々。バケツやスコップや型抜きなどを上手く使いこなすのも工夫が必要です。子どもたちが自分で考え、それらの物を使うことで自然と道具の使い方を理解することができます。保育士さんがレクチャーしなくても大丈夫!といったこともあるかもしれませんね。
山や川などを作る
泥を集めてどんどん積み上げて山やお城を作ったり、泥に水を湿らせて川を作ってみましょう。山やお城は水を加えて、泥を上手く湿らせながら作ってみると崩れにくいですよ。まだ手先が器用ではない子は山や川を自分一人でうまく作ることは難しいかもしれません。そんな時は、保育士さんや周りのお友達と一緒に作ることで作業が楽になります。子ども達と一緒に泥を使って製作物をすることで完成したときの達成感を一緒に味わったり喜んだりすることができますよ。
泥んこ遊びの指導ポイント
発達に合わせた遊びをしよう
子どもの発達に合わせた遊びを心がけましょう。乳児は特に砂に触れたことがない子たちが多いと思います。手指や腕を自由に動かせない子供は、山を作るといった高度な遊びは難しいです。0歳児から2歳までの子たちは砂に慣れさせる。3歳から5歳まではお友達と一緒に達成感を味わうことができる遊びをするといった発育に合わせた遊びを設けることで上記に記載した泥んこ遊びの効果が適切に発揮されますよ。
安全管理をしっかりする

子どもが誤って泥を口に入れてしまったり、道具を使う時に誤飲しないように見守りましょう。目を離さないといった基本的なことも意識することが大切です。泥遊びは、裸足で遊ぶことが多いと思います。尖ったものを足に刺したりといったことがないように事前に安全を確かめた上で遊びましょう。外で遊ぶときは虫刺されにも注意したいですね。泥で遊んだ後は、感染症予防のために必ずハンドソープで手を洗うことが大事です。保育士さんが常に遊び場所の安全管理を怠らないようにしましょうね。
こまめに休憩をとる
遊びに夢中になっていると休憩を取るのを忘れがちです。こまめに休憩時間を設けるようにしましょう。大体1時間ほど遊んだら休憩を取ることをおすすめします。夏場に遊ぶときは熱中症や脱水症状の危険性も上がりますので保育士さんは注意が必要です。水分や塩分の補給も忘れずに行いましょう。まだ幼い子は自分の体調を上手に把握できないうえに、体調の変化をうまく伝えられません。保育士が子どもの体調不良のサインを見逃さないようにすることが肝心です。保育士さんは子ども達の健康状態を常に配慮をして、思いっきり遊びを楽しめるように心掛けるようにしましょうね。
着替えを用意する

泥んこ遊びは服が泥で汚れてしまうことが避けられません。汚れてもいいようにあらかじめ着替えを用意しておきましょう。泥んこ遊びをする前に、連絡帳や送り迎えの際などに保護者に泥んこ遊びをするので着替えの用意をお願いするようにしてください。服もそうですが、靴の替えの用意もお忘れなく。着替えを用意することで子ども達は汚れても気兼ねなく遊ぶことができますね。
みんなが楽しく遊べてるか常に気を配る

泥んこ遊びの注意点は安全面や服装ばかりではありません。みんなで楽しく遊べているかにも気を配ることが大切です。子どもの中には泥を触るのが苦手な子もいると思います。一人一人に合わせてどんな遊びをするかということも考慮して遊びを選ぶことが大事ですね。なるべくどの子も公平に楽しめるような泥んこ遊びができるように保育士さんがちゃんと仕切ってあげましょう。
様々な遊びを取り入れよう

同じ遊びばかりでは飽きてしまいます。新しい遊びを取り入れましょう。上記で紹介したように泥んこ遊びにおすすめのものは多くの種類があります。ぜひ園で取り入れてみてください。出来るだけ多くの遊びを取り入れることで子ども達は様々な能力を身につけることができます。子ども達の得意不得意を観察してみたりといった保育士さんの工夫次第で遊びの幅はどんどん広がりそうですよ!
まとめ
泥んこ遊びは幅広い年齢で楽しめる遊び
本記事では、保育でできる泥んこ遊びについてご紹介しました。いかがでしたでしょうか。泥んこ遊びは運動能力の向上や社会性や協調性が身についたりと様々な効果をもたらすことが分かりましたね。子どもが泥を舐めてしまったり、お友達に泥を投げるようなことが無いように注意することが必要です。子どもたちが怪我無く安心して遊べる配慮を行いましょう。泥んこ遊びをした後は、爪の中までしっかりハンドソープで洗って手を清潔にしましょうね。今回紹介した遊びのアイディアを参考に、是非子ども達と泥んこ遊びを楽しんでください!
※本サイトは全国の保育園・幼稚園で働いてる人、これから保育士を目指す方への情報提供を目的としています。
掲載された情報をご利用いただいた結果、万一、ご利用者が何らかのトラブル、被害、損失、損害等が発生したとしても、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
よくある質問
保育士くらぶにはどんな記事がありますか?
保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。
保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?
最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。
保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?
保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。