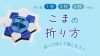子どもは褒められた分だけ成長します。ですが、子どもを褒めることはとても難しいですよね。子どもを褒めるときは、すごいと言うだけでは褒める意味がありません。何が良かったのかを具体的に伝えることが子どもの成長に繋がります。では、どのような褒め方が子どもの成長に効果的なのでしょうか?今回は、そのような悩みの方に向けて、子どもを褒めるコツや注意点について解説していきます。今回の内容を参考に、正しい褒め方を実践して子どもの成長の幅を広げましょう!
子どもを褒める5つのメリット
子どもが自信を持つ

子どもを褒めることにはメリットがいくつかあります。1つは子どもが自信を持つという点です。ご自身の体験を思い返してみてください。例えば学生のときにテストでいい点をとることが出来た時や、仕事で期待以上の成果を出すことが出来た時、先生や上司に褒められるとどのような気持になりますか?嬉しいですよね。認められて嬉しいという気持ちによってモチベーションが高まり、自信が生まれます。
子どもの自己肯定感を高める
自信を持つということは、自己肯定感を高めることに繋がります。自己肯定感が高まると幸福度が得られたり、ネガティブな感情を抱きにくく失敗に強くなるほか、他人と比較して落ち込むことが少なくなるという効果も。このように自己肯定感は人生において大きなメリットをもたらしてくれます。子どもを正しく褒めて自信を持たせることが出来れば、褒めるという行為は彼らの将来に直結する良い行為だといえますね。
子どもが素直になる
子どもを褒めるメリットの4つめは、子どもが素直になるという点です。先程まで、子どもは褒められると自信を持ち自己肯定感と自主性が高まると解説してきました。上記の3点において成長することで、子どもは物事に対して素直な姿勢で向かうことが出来るようになります。子どもは叱られるとふてくされたりいじけたりしますよね。ですが、素直になることで自分の行いを反省し、ポジティブかつ謙虚な姿勢で改善を出来る人間になれます。子どもには大きくなった後も人として立派な存在でいてほしいですよね。
子どもとの信頼関係が深まる

そして、子どもを褒めることで保育士と子どもとの信頼関係が深まります。保育において、子どもと保育士間の心の距離はとても重要ですよね。褒めるということは、子どもを認めるということに繋がるため、大人に認められた子どもは自分を評価してくれた大人に対して信頼感を抱きます。そして子どもは、この先生は自分の事をしっかり見てくれていると安心して一日を過ごすことが出来ます。保育士として働くからには、一緒にいて子どもに安心感を与えられる存在でありたいですね。
褒めるときの4つのコツ
結果だけでなく過程も褒める

褒める際は、結果だけでなく子どもが取り組んだ過程も褒めるようにしましょう。子どものうちに重要なのは、何を成し遂げたかよりも何を努力したのかをしっかり褒めること。過程の努力を褒めてあげることで、子どもの自主性や自己肯定感を高めることが出来ます。そして、努力を褒められた子どもは何事にも努力する姿勢を身につけ、その姿勢は彼らが大人になってもきっと活かされるでしょう。
どんなことが出来たのか質問する
また、褒める際はどんなことが出来たのかをあえて質問してみましょう。先程過程を褒めるとお伝えしましたが、子ども本人に出来たことを聞いてみると、保育士が気づかなったことが発見出来ることがあります。客観的にみて良かった事以外にも、本人が良いことだと思ってしたことも沢山あります。子どもの良心をしっかり認めてあげることで、子どもはあなたの事を信頼出来る大人だと判断してくれますよ。
感謝の気持ちを伝える

そして、子どもたちを褒めると同時に、その行為に対しての感謝の気持ちも伝えましょう。ありがとうという感謝の言葉は言われると嬉しいですよね。保育士側からありがとうと伝えることで、子どもは1人の人間として感謝されていることに対して誇りと自信を持ちます。また、子どもは感謝をされると嬉しいと学ぶので、他の子にも素直に感謝する気持ちが育まれますよ。感謝はする側もされる側も得しかありませんので、積極的に取り入れていきましょう。
アイメッセージを活用する
アイメッセージとは、臨床心理学者トマス・ゴードンが提唱したもので、自分自身を主語にした話し方を言います。「私はあなたが手伝ってくれて嬉しい」というように私自身を主語にすることで、ストレートな気持ちを子どもに伝えることが出来ます。子どもが何か達成したときに、保育士側がアイメッセージを活用して感謝の気持ちを伝えることで、子どもとの信頼関係が深めることが出来ますよ。
褒めるときの3つの注意点
過剰に褒めすぎない
褒める際は過剰に褒めすぎないようにしましょう。子どもがした行為の価値以上に褒めると、かえって子どもに不信感を抱かせる恐れがあります。あまりに褒めることにこだわると、この先生は自分に気に入ってもらおうとして沢山褒めてくるのではないかと子どもに感じられてしまいますよ。子どもの行為をしっかり見てあげて、行為に適した褒め方を心がけましょう。子どもをよくみて良いなと感じた部分を具体的に褒めてあげることで、子どもから信頼される存在に近づきます。
なんでも褒めることはしない
また、なんでも褒めることをしてはいけません。些細な事を毎回褒めていると、子どもは褒められることに慣れていきます。褒めるときは過程の努力を褒めるべきだと伝えましたが、褒められることに慣れてしまっては、その先の成長が見込めません。小さな事は一度褒めたら褒めることをやめ、子どもがチャレンジしたもっと大きなことについて褒めるようにしていきましょう。その積み重ねが、子どもが人として大きくなる土台となりますよ。
他の子と比較して褒めない
「〇〇君よりもよく出来たね」などと、他人と比較して優れている点を褒めることはしないようにしましょう。本人が周りと比べて努力をすることは良いことです。しかし、第三者が子供同士を比較して褒めても、子どもたちはいい思いをしません。比べる相手は昨日の自分です。子ども本人の努力や結果を褒めることで、子どもに昨日の自分より少し成長したと感じさせることが保育士の役割ですよ。
叱るときも褒めよう
良かったところを伝える
子どもがいたずらをした時、叱るだけでなく褒められる部分はなかったかを探す努力は大切です。結果的には良くないことでも、もしかしたらその行為は子どもが良いことだと思ってしたものかもしれません。その場合はその気持ちを尊重して汲み取ってあげましょう。叱られただけの子どもよりも、同時に褒められた子どものほうが保育士が伝えたいことを聞き素直に反省し、学びとして次の機会へ活かすようになりますよ。
褒めと叱りのバランスが大事
しかし、叱りと褒めのバランスはとても重要です。叱ると同時に褒めることは子供の成長に効果的ですが、かといって褒めすぎると子どもは叱られたことを忘れ、また同じ過ちを繰り返してしまうかもしれません。叱る際は、叱るべき部分をしっかりと子どもに理解させましょう。叱られただけでは子どもは落ち込んでしまいやすいので、そのネガティブな感情を少し和らげる程度の比重で褒められるとよいですね。
上手な3つの叱り方
ダメな理由をしっかり伝える
ここでは叱る際に大切なポイントを3つご紹介します。1つはダメな理由をしっかり伝えるという点です。子どもがした行為のどこが悪かったのかを子どもに理解させることで、子ども自身は自分がした行為のどこが悪かったのかを把握することが出来ますよ。何が悪かったかを知ることは、反省し次に繋げるために必要なことです。子どもが同じ過ちを繰り返さないように、叱る際には叱る理由をしっかり伝えましょう。
威圧的でなく寄り添った伝え方をする

また、ダメな理由を伝える際は威圧的になってはいけません。一方的にどこが悪かったかを言いつけたり声を荒げて叱ったりすると、子どもからは距離を置かれる存在になりやすいですよ。叱るといっても子どもが悪かった行為を改善出来るようになればよいので、子どもに寄り添った接し方を心がけましょう。しかし、甘やかすことと寄り添うことは別です。口調に気をつけて、伝えるべきことは厳しくてもはっきりと伝えましょう。
どうすればよかったか一緒に考える
また、何が悪かったかを伝えたあとは、どうすれば叱られなかったかを一緒に考えることをおすすめします。ただ叱るだけでは、子どもには叱られた記憶しか残りません。叱ったあとに子どもと改善策を考えることで、その後の改善に繋がります。保育士側から答えは言わず、質問して子どもに考えさせるとより効果的ですよ。そしてこのコミュニケーションをとるためには、寄り添った態度が不可欠です。威圧的な態度では子どもは萎縮したり言うことを聞かなくなってしまうので、焦らず冷静でいることを意識しましょうね。
子どもをよく観察しよう
子どもの伸ばせる部分は沢山ある

子どもの成長を伸ばせる部分は沢山あります。素直になる気持ちや相手を思いやる気持ち、自分を大切にして自信を持つ姿勢など、それらの内面的な成長には保育士のサポートが欠かせません。褒めるという行為は子供の内面的な成長に深く関わります。上手に褒めて子どもを伸ばすために、普段から子どもをよく観察してふれあいを欠かさないようにしましょう。些細なことでも、子ども一人ひとりが何をしているのか把握することを常に意識出来るといいですね。
まとめ
子どもの個性に合わせた褒め方をしよう

いかがでしたでしょうか。子どもを褒めることで、子どもは自信を持ち内面的に成長します。その成長は一時的なものではなく、子どもたちが将来大人になるための第一歩になります。保育士側は、その成長のサポートをする立場として寄り添ったコミュニケーションを心がけましょう。また子どもは一人ひとり個性があるので、それぞれに合わせた寄り添い方をすることでより信頼関係を深めることが出来ます。この記事を参考に、ぜひ実践してみてくださいね。
よくある質問
保育士くらぶにはどんな記事があります
保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。
保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?
最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。
保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?
保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。