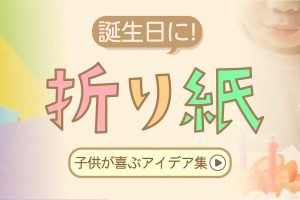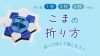目次
日々目まぐるしいスピードで成長していく1歳の子どもたち。それに伴い、自らの意思で体を動かせるようになるので、遊びにも注意をする必要があります。保育で行う遊びはただ子ども達と遊ぶだけでなく、子どもの成長を促進するためにどのような遊びを行うべきかを考えて行う事も大事です。今回はそんな1歳児の運動遊びについて詳しくご紹介します。子ども達との遊びがマンネリ化してきた方や日々の遊びが思いつかなくてお悩みの保育士さんは必見ですよ。
1歳児と楽しめる!運動遊び
マット運動

まずは、マットの上でコロコロしたり、ハイハイしたりといった簡単なものからはじめてみましょう。マットの上でコロコロすることは、平衡感覚を鍛えるのにはもってこいの遊びです。ですが、やりすぎは目が回り気分が悪くなってしまうことがあるので注意が必要。マット遊びにはマットの感触を楽しみながら体を動かして遊ぶことができるといった大きなメリットがあります。怪我の予防として、マットが滑らないように滑り止めシートを敷いておくことをおすすめします。
ボール遊び

ボール遊びの最大のメリットとしては運動能力の向上がとても期待できることです。あまり大きすぎず、柔らかいボールを使用しましょう。1歳児はまだ遊びのルールをうまく理解できません。まずは、ボールをコロコロ転がしてみたりとルールがない遊びを提案してみるのはいかがでしょうか。保育士さん細心の注意を払って子ども達に怪我がないよう遊べるように心がけたいですね。
かくれんぼ

かくれんぼは、鬼を決めて、鬼に見つからないように隠れるといったシンプルで小さい子でも楽しめる遊びです。鬼は一人と限定せず、何人も鬼がいたり、時間制限を設けたりするとさらにかくれんぼが楽しくなるでしょう。また、かくれんぼをするときは公園の外には出ないように子ども達に注意喚起を行いましょう。子どもが園の外で迷子になり行方不明になってしまっては大変です。隠れる場所は必ず園の中に限定するようにしてください。
真似っこゲーム
何の真似をしているのかを当てるシンプルなゲームです。前に出て、動物を始めとした身の回りのものを再現した動きをし、他の人は、その姿を見て何の真似をしているのか当てます。まずは、保育士さんがお手本を見せてあげると導入がしやすいです。慣れてきたら、子どもたちが真似っこする側に回っても面白いかもしれませんよ。動物、有名人、アニメの人気キャラなどお題を決めるとなお楽しめますね。
ダンスや体操
ダンスや体操は全身を動かすので、効率よく運動遊びを取り入れることが出来ます。また、ダンスをいきなり行うのではなく最初は体操から取り入れ体をほぐし、徐々に動きを大きくしていきましょう。保育士さんが声掛けをしながら行うことで導入がしやすくなりますよ。運動だけでなく子どもたちのリズム感を養うことが出来るので、是非取り入れたい運動遊びの一つですね。
リトミック
リトミックとは、音楽に合わせて体を動かす音楽教育のこと。音を体で感じることができるリトミックは、幼児教育に最適と言われており多くの園で取り入れられています。リトミックは、能力の発達だけでなく、お友達と活動する楽しさを感じられるため協同性の向上に繋がります。また、音楽やリズムに触れながら、子供達の想像力や感性を養うこともできます。音楽と身体表現を組み合わせたリトミックも室内でできる遊びの一つ。ぜひ室内遊びに取り入れてみてはいかがでしょうか。
新聞紙で玉入れ
新聞紙遊びは身近にある素材で手軽にできる遊びです。まずは新聞紙という素材に子どもを慣れさせることから始めましょう。子どもが新聞紙に慣れた後に、下記でご紹介する新聞紙で玉入れを行ってみてください。
- 子どもたちは新聞を破り、丸めてボールをたくさん作る。
- 保育士はカゴを持って立つ。
- 子どもたちはボールをカゴに投げ入れて競争する。
保育士が移動して、子どもたちは追いかけながら玉入れをするなどの工夫をする事でさらに新聞紙遊びが楽しくなるでしょう。1歳児の子どもは、ねらい通りに物を投げるのがまだ難しいので、カゴはなるべく横に広くて口が大きいものを使いましょう。
遊具で遊ぶ
ブランコやすべりだい、鉄棒などといった園に設置されている遊具を子ども達の好きに遊ばせましょう。遊具の種類によって子ども達は自分の得意不得意を見極める力も養うことができます。遊具の種類によって、夏場はとても熱くなり子どもが火傷をしてしまうことも予想されます。事前に遊具が子ども達が触れて問題ない温度かを確認してから遊ばせましょう。遊具の対象年齢や一度に乗って大丈夫な人数も確認しましょう。実は、遊具を使った遊びは稀に死亡事故が起きてしまうことがあるのです。子どもたちを監視することや一緒に遊んだりしてその場で何かがあってもすぐに対処できるように心がけましょう。
1歳児の特徴

言葉の発達
1歳になると少しずつ言葉を知り、話せるようになります。相手の言葉を理解し、真似をすることや返答できるようになり始めるのもこの頃ですね。「ママ」「パパ」「わんわん」などといった簡単な言葉を話せるようになります。1歳になりたての頃は、1語で簡単な言葉しか話せなくても、1歳後半には2語話せるようになる子どもも多いです。子供の言葉の発達には、周囲の大人が積極的に話しかけてあげることが重要です。子どもの口調に合わせて簡単な言葉でゆっくり話しかけてあげましょう。
自我が芽生える
心と体の発育に伴って自分の意志が強くなり、自我が芽生え始めるのが1歳児の時期。日常の様々なことに喜怒哀楽を示すようになります。自我の芽生えによって自分がやりたいことが明確になってくるのです。子どもに色んなことを積極的にチャレンジさせましょう。1歳児はまだ自分の身を脅かす危険な行為について理解することが難しいです。そのため、保育士さんがしっかり見守ってから子供がやりたいことにチャレンジさせることが大事になってきます。
一人歩きができるようになる
ハイハイ歩きを卒業し、いよいよ2足歩行が出来るようになり始めるようになります。最初はよちよち歩きや伝い歩きですが、1歳後半になるにつれ徐々に1人で歩けるようになります。歩行が安定していない頃は、よく転んでしまったり出来なくて泣いてしまうこともよくあるかもしれません。1人歩きの練習には危険も伴うので、周囲の大人がきちんと見守りサポートしてあげることが大切です。子どもたちが安全に歩けるような環境作りも意識しましょう。
1日3食になる
1歳になると、母乳やミルクを卒業し、離乳食が食べられるようになります。1歳児の食事では、1日3食が基本です。食事の時は、無理やり食べさせるのではなく食べることの楽しさを子どもに感じてもらえるように促しましょう。お友達や先生と食べる喜びを感じてもらえるとなおいいですね。発育の状況によって食べ られるものが子ども1人1人違います。また、お家で食べたことはないけれど実はアレルギーだったという事もあるので子どものアレルギーの有無は入念に保護者の方に確認しておくようにしましょうね。
運動能力が上がる
子どもが運動習慣を身につけると、運動能力の向上、病気や怪我の予防に繋がります。1歳児は、運動能力が身に付き始めて外に出かけて遊具や砂場などで遊んだりすることが出来るようになります。1歳児の体は発達途中でまだまだ不安定なので安心安全に運動ができる環境作りを心がけましょう。運動習慣を身につけないと、摂取エネルギーと消費エネルギーをバランスよく保つことができず肥満になってしまい、様々な病気にかかりやすくなってしまう可能性があります。そのため、子どものうちから運動習慣を身につけることが重要になるのです。
手先が器用になる
1歳児は脳の発達により、手先を使った細かい動きが出来るようになってきます。
- 食事の時にスプーンやフォークを使って自分でご飯を食べられるようになる
- ドアノブを回してドアを開ける
- ペンやクレヨンで器用に線や絵を描けるようになる
などといった上記に挙げたことが徐々に1人で、できるようになります。1歳児の発育には個人差があるため、うまくスプーンやフォークを動かせないという子もいます。まだ手先を動かすことに慣れない1歳児には、手先が器用になるためのおもちゃを取り入れてみてもいいかもしれませんね。
運動遊びの注意点

安全面に気をつける
1歳児は、危険な行動がまだ理解できない年齢です。1歳児が遊びをするときは特に安全面は気をつけましょう。子どもが誤って口に入れてしまいそうなものは使用を避けたり、誤飲すると特に危険なものは極力扱わないようにしましょう。また、目を離さないといった基本的なことも意識することが大切です。扱うものによっては子供のアレルギーチェックもきちんと行いましょう。外で遊ぶときは虫刺されにも注意したいですね。保育士さんが常に子ども達の遊び場の安全管理を怠らないようにしましょうね。
子どもの好奇心を阻害しない
1歳児は何でも「自分でやってみたい!」という意欲が出てくる時期。子供の好奇心を大事にしてあげましょう。子どもに危険がないようにサポートしてあげることはとても大切なこと。しかし、保育士さんがサポートやりすぎてしまうとかえって子供のやる気が削がれてしまうことがあります。子どもへのサポートは加減が大事なのです。なんでも保育士さんがやるのではなく、危険なこと以外は基本的に子どもに任せるようにしましょう。
なんでも褒める
1歳児には、些細なことでもとにかく褒めて伸ばすことを意識しましょう。子どもは褒められることで認められた気持ちになり嬉しくなります。「またやってみよう!」と自分からチャレンジしたり物事を前向きに取り組んだりするのです。結果だけでなく、頑張った過程を褒めてあげましょう。過程まできちんと褒めてあげることで、子どもの自己肯定感を高めることにも繋がります。保育士さんが保護者に子どもが頑張った姿を伝えることでママやパパにも褒められて子供はとてもいい気分になるでしょう。
不審者に気をつける
運動遊びの中でも外で遊ぶものは不審者にも気を付けなければいけません。危険を察知したら、防犯ベルやスマホなどで知らせる、近隣に助けを求めるといった行動を起こすことも重要です。再犯防止のため、不審者が出たときは念のため警察に連絡する事をおすすめします。日頃からできる対策として、マニュアルを作成して職員全員がいざという時に連携を取れるようにしておくと不審者への対応もスムーズにいくかもしれませんね。
まとめ
充実した運動遊びを!

今回は、保育園や幼稚園で取り組める1歳児の運動遊びについて幅広くご紹介しました。いかがでしたでしょうか。子どもは運動遊びを通して、さらに大きく成長することが出来ます。また、保育士さんが子供の遊びに介助するポイントとして、安全面に気をつける事とサポートをしすぎない事を心がけましょう。本記事でご紹介した運動遊びのアイディアや注意点を日々の保育にぜひ取り入れてみましょう。
よくある質問
保育士くらぶにはどんな記事がありますか?
保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。
保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?
最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。
保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?
保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。