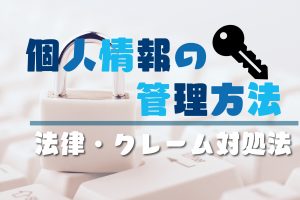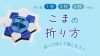目次
こんにちは!保育士くらぶ編集部です。
保育士くらぶでは、保育現場で明日から使える最新トピックや保育士さんの転職、キャリアをサポートするコンテンツをおとどけしています。
求人情報や転職・キャリアのご相談は同グループが運営する保育園の離乳食やミルクの進め方
赤ちゃんの離乳食を始める時期は、生後5ヵ月頃からというのが一般的です。 ちょっと古い資料ですが、厚生労働省策定の「授乳・離乳の支援ガイド」(平成19年3月)でも、離乳食の開始時期は生後5ヵ月が47.6%と最も多い回答になっています。 厚労省策定のガイドラインでも、以前は離乳食を4つの段階に区切って進めるように推奨していましたが、個人差を考慮して進めるように区分はなくなりました。 しかし、管理栄養士さんと一緒に計画的に離乳食を進める保育園では、この段階的な離乳食の進め方を採用している施設が多いようです。離乳食を与えるタイミングも、園それぞれです。 今回は、保育園における離乳食についてリサーチしました。0歳児クラスを初めて担当する新米保育士さんにも、ぜひチェックして欲しいです。 離乳食を開始する時期は、赤ちゃんの成長の度合いによって個人差が出るのは当然です。その目安として以下のような兆候があります。 離乳食をスタートするこの時期のメニューとしては、10倍粥が最もポピュラーなものと言えます。粒が残らない程度まで潰して食べさせてあげましょう。 他には、トロトロになるまで茹でてから潰した玉ねぎやジャガイモ、ヒラメなどの魚を茹でてからする潰したものなどがいいようです。 離乳食の与え方について解説している動画も見つけたので、こちらも参考にしてみてください。離乳食【初期(5・6ヵ月)編】

献立・食べさせ方
回数
この時期は、あくまでも食べるための訓練程度なので、栄養はミルクや母乳で摂取しながらゆっくり進めましょう。
離乳食の回数の目安は、1日1回です。授乳は1回200mlを4~5回が目安です。
離乳食【中期(7・8ヵ月)編】

初期段階の離乳食を喜んで食べ始め、下痢・便秘といった症状が出ないようであれば次の段階に進みましょう。この頃になるとちゃんと座れるようになり、早ければハイハイや伝い歩きもできるようになります。
また、柔らかいものなら舌と上あごで潰して食べることができるようになります。
献立・食べさせ方
中期のメニューは、7倍粥から始め5倍粥・3倍粥・全粥という風に少しずつ様子を見てステップアップしましょう。
他には、ささみなどの脂身の少ない肉を茹でてから潰したものと、ニンジンや大根の煮たものを潰したペーストを混ぜ合わせたもの。
豆腐を細かくみじん切りにしたものは、最初は2mm角くらいからはじめて少しずつ大きめにしていきましょう。
また卵や乳製品はアレルギーが出やすい食品なのでまずは少量から様子を見ましょう。
こちらは、うどんを使ったレシピです。
回数
回数も1日2回くらいですが、あくまでも目安ですので食べ具合を見て調節しましょう。この時期の授乳は、1回200mlを3~4回程度です。
離乳食【後期(9・10・11ヵ月)編】

このころになると、ハイハイやつかまり立ち、伝い歩きをし始めます。歯も少しずつ生え揃ってくるため、噛んで食べることができるようになります。
手でつかんで食べたがりますが、無理にやめさせないで自由に食べさせましょう。
献立・食べさせ方
この時期のメニューは、お粥から徐々に柔らかく炊いたご飯に換えていきましょう。
ニンジンやさつまいも、りんごなどを手づかみでも食べやすい大きさに切って、砂糖を使わずに煮たものも喜んで食べます。バナナのような柔らかい果物なども食べられます。適当な大きさに切って食べさせてあげましょう。
こちらは、レンジで簡単にできるハンバーグのレシピです。
回数
離乳食の回数は、1日2~3回が目安です。授乳は200mlを1日2~3回程度で。
離乳食【完了期(1歳~1歳半)編】
少しずつ言葉も発するようになるこのころは、ひとりで歩けるようになるなど運動量も増えますから、食べる量も多くなっていきます。
また、少し生えた前歯で上手に噛み切ったり、歯茎で噛んで潰したりもうまくなり、食べられるものも増えていきます。
スプーンやフォークに興味を持ち始めたら、持たせてあげましょう。まだ上手には使えませんから、食べさせてあげるか手づかみで食べさせましょう。
献立・食べさせ方
豆腐やジャガイモを潰したハンバーグやコロッケなど、手で持って食べられる大きさで作ってあげましょう。人参やカボチャで作る蒸しパンやマフィンなども、砂糖を使わないレシピで十分甘く作れます。
授乳はいつまで!とはっきりした答えはありません。離乳食を1日3食しっかり食べるようになると、自然に飲まなくなるという子もいれば、食後にしっかり飲む子もいます。
保護者とも相談の上、卒乳児期を考えましょう。
こんな時はどうする!?離乳食FAQ
最後に、離乳食についての注意点です。
・栄養バランスのとりかたは?
3つの食品グループから1つずつチョイスしましょう。
- ビタミン・ミネラル…野菜・きのこ・果物など
- エネルギー源…ご飯・パン・めん類・イモ類など
- タンパク質…魚・肉・乳製品・卵・大豆など
管理栄養士さん、保護者としっかり連携が必要です。
・食べない、飲まないときはどうする?
思ったより食べてくれなくても、焦らずに見守りましょう。保育士さんの場合、ほかの子のお世話もあり時間に余裕はないかもしれませんが、無理強いは禁物です。
ステップアップしてダメなら、前に食べさせていた離乳食に戻ってみるのも手です。
・楽しく食べてもらうためには?
食べたら少し大げさにほめてあげましょう。
怒ったり無理強いしたりせず、食に興味を持てるような雰囲気作りも必要です。保育士さんが食べるふりをして、食事は楽しいという雰囲気を伝えてあげるのも良いですね。
・アレルギーから守るには?
園児個々のアレルギーやNG食材は、保護者と事前に綿密に情報交換し、管理栄養士・保育士・保護者の3者間での認識を統一しましょう。
また、保育士間の申し送りなども、徹底することが大切です。
さいごに
保育園の離乳食に関するまとめ、いかがでしたでしょうか?
赤ちゃんがすくすく成長していくために大事な離乳食。
家庭と連携しながら、赤ちゃんが楽しく食べられるような離乳食の計画を立てましょう!