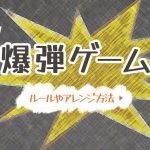パラバルーンという遊びを聞いたことがあるでしょうか。実際にやったことがあるという人もいるかもしれませんね。今回は、パラバルーンについて紹介していきます。そもそもパラバルーンは、表現を楽しむ遊び。遊びとはいっても、運動会の出し物にもぴったりなお遊戯とも言えます。パラバルーンには、さまざまな技がありますが、ものによっては保育士のサポートが必要なものもあります。そのため、保育士も一緒になって楽しむことができますよ。ぜひこの記事を参考に、イベントに取り入れてみてはどうでしょうか。
パラバルーンとは
カラフルで大きな丸い布を用いて表現を楽しむ遊び
パラバルーンとは、カラフルで大きな丸の形をした布を用いて、表現を楽しむ遊び。大きな丸い布を全員で持って、動かしたり、形を作ったりします。それほど難しいテクニックなどは必要ではないので、低年齢の子から5,6歳の子まで幅広い年齢で楽しむことができますよ。また、ただ楽しいだけでなく、友達と協力することで協調性や体力と筋力の向上にもつながります。一石二鳥以上の効果があるので、ぜひやってみてくださいね。
運動会の出し物にも

パラバルーンは、運動会の出し物としてもおすすめ!パラバルーンは子供たちが協力して1つの出し物を完成させる様子を保護者の方に披露するのにもってこいです。この記事でご紹介する基本動作や応用動作を組み合わせて演目を作ってみてくださいね。リズムや曲に合わせて行うと迫力ある出し物になりますよ。また曲を変えるだけで雰囲気も変わるので、毎年の恒例プログラムにしても面白いと思いますよ。
パラバルーンのねらい
協調性を育む

ここからは、パラバルーンのねらいを3つご紹介します。1つ目は、子供たちの協調性を育むこと。パラバルーンは、丸い大きな布を使用しますよね。そのため、決して1人で扱うことはできませんよね。その上、みんなでタイミングを合わせなければ技を披露することはできません。時には、臨機応変な対応が必要になるときもあるでしょう。友達と協力が不可欠であるからこそ、子供たちの協調性を育むことができますよ。
一体感を楽しむ
2つ目は、一体感を楽しむこと。先ほどもお伝えしたように、パラバルーンはみんなで協力して行うもの。クラスやグループ単位で協力して技を行うことで一体感を感じることができます。みんなで1つの技を成すという目標を掲げて行動すると、実際に成功したときに得られる達成感はとても大きなものですよね。パラバルーンでは、子供たちに一体感を感じてもらえる上に、それによって得られる楽しさも感じてもらうことができますよ。
体力や筋力の向上

3つ目は、体力や筋力の向上。パラバルーンは大きな丸い布を扱いますよね。みんなで持っている多いな丸い布を頭上に掲げたり逆に床につけたりして行います。そのため、体力や筋力がある程度必要になりますよね。また、外で行う場合には風の影響を受けるので、さらに風に耐える筋力が必要になりますよね。パラバルーンを行うだけで、子供たちの体力や筋力の向上をサポートすることができますよ。パラバルーンを行うことには、多くのメリットがあるのでぜひ取り入れてみてくださいね。
パラバルーンの基本動作
①おせんべい
ここからは、パラバルーンの基本動作を4つご紹介します。基本動作はパラバルーンの技のベース。他の技と組み合わせたり、アレンジをしたりすることもできますよ。まず1つ目は、おせんべい。
①パラバルーンを囲んで、両手でパラバルーンのふちを持つ
②タイミングを合わせて自分の方にパラバルーンを引っ張る
③パラバルーンがぴんと張った状態になる
この状態を、おせんべいと呼びます。
②小波
パラバルーンの基本動作の2つ目は、小波。
①パラバルーンを囲んで、両手でパラバルーンのふちを持つ
②その場にしゃがむ
③しゃがんだまま、パラバルーンを上下に小さく動かす
すると、小波を表現することができます。周りの子たちとタイミングや動かす幅を合わせなければ、きれいな波には見えなくなってしまうので、はじめはお手本を見せてあげるといいかもしれませんね。また、地面にパラバルーンが当たると、砂埃が立ちやすくなるので少し宙に浮かして行うと良いですよ。
③大波
パラバルーンの基本動作の3つ目は、大波。
①パラバルーンを囲んで、両手でパラバルーンのふちを持つ
②立ったまま、パラバルーンを上下に大きく動かす
すると、大波を表現することができます。小波を表現する時同様、パラバルーンを動かす幅やタイミングが重要。カウントをとりながら行ってみるのもいいかもしれませんね。とても大きく動かすというよりかは腰の高さから首の高さくらいの幅で動かすのがおすすめですよ。
④横波
パラバルーンの基本動作の4つ目は、横波。
①パラバルーンを囲んで、両手でパラバルーンのふちを持つ
②立ったまま、パラバルーンを左右に大きく動かす
すると、横波を表現することができます。横波を表現するのは、小波や大波よりも少し難しくなります。左右のどちらから動かし始めるのか事前に決めておくといいかもしれませんね。パラバルーンから手が離れやすくなる技なので、しっかり持っておくよう子供たちに伝えておきましょう。
パラバルーンの応用動作
①お山
ここからは、パラバルーンの応用動作をご紹介します。まず1つ目は、お山。
①パラバルーンを囲んで、両手でパラバルーンのふちを持つ
②タイミングを合わせて、両手で勢いよくパラバルーンを上げる
③合図に合わせて、パラバルーンのふちを地面につける
④パラバルーンの中心に空気が入り、中心が膨らむ
すると、お山を表現することができます。しゃがむタイミングがずれてしまうと歪んだお山になってしまうので、合図に合わせて一斉にパラバルーンのふちを地面につけられると良いですね。
②飛行機

2つ目は、飛行機。
①パラバルーンを囲んで、片手でパラバルーンのふちを持つ※このとき、全員同じ方の手で持つこと
②全員で同じ方向を向き、パラバルーンを持っていない方の手を横にのばす
③円を描くように歩く
すると、飛行機を表現することができます。③の円を描くように歩いているときに場所が移動することがないように、足元に目安となる印をつけておくといいかもしれませんね。
③シーソー

3つ目は、シーソー。
①パラバルーンを囲んで、パラバルーンのふちを両手で持つ
②合図に合わせて、片側半分の子供たちは勢いよくパラバルーンを下げながらしゃがむ
③もう一方の子供たちは勢いよくパラバルーンを頭の高さまで上げる
④次の合図で、しゃがんでいた子供たちは勢いよくパラバルーンを頭の高さまで上げる
⑤頭の高さに上げていた子供たちは、勢いよくパラバルーンを下げながらしゃがむ
この②〜⑤の動作をリズム良く繰り返すことで、シーソーを表現することができます。
④ロケット
4つ目は、ロケット。
①パラバルーンを囲んで、パラバルーンのふちを両手で持つ
②合図で勢いよく腕を上げ、パラバルーンを高く上に掲げる
③腕を上げたまま、中央に向かって走る
④パラバルーンの中央に空気が入り、パラバルーンがフワッと膨らむ
すると、ロケットを表現することができます。このとき、全員で息を合わせて同じスピードで中心に集まることがポイント。目安となる中心地点に印をつけておくといいかもしれませんね。
⑤きのこ
5つ目は、きのこ。
①パラバルーンを囲んで、パラバルーンのふちを両手でもつ
②勢いよく腕を上にあげ、少しずつ中心に集まる
③パラバルーンが空中にある間に、全員で持っている左右の手を持ち替えて外側を向く
④合図に合わせて勢いよくパラバルーンを下ろして、子供たちは内側に入る
⑤パラバルーンのふちを地面につけ、空気が抜けないようにする
すると、きのこを表現することができます。このとき、左右の手を持ち替える時に風に煽られて、パラバルーンが飛んでいかないように注意するよう伝えましょう。
⑥花火

6つ目は、花火。
①パラバルーンを囲んで、パラバルーンのふちを両手でもつ
②保育士がパラバルーンの中心にペットボトルのキャップにビニールテープを巻いたものを投げ入れる
③合図に合わせて、パラバルーンを勢いよく上に持ち上げて勢いよく下に降ろす
④パラバルーンの上で、ペットボトルのキャップが打ち上がる
すると、花火を表現することができます。この技は、事前に準備をする物があるため、最後の大技として技構成に取り入れるのがおすすめですよ。
パラバルーンを行う際におすすめの曲
WAになって踊ろう
ここからはパラバルーンを行う時におすすめの曲を5つご紹介します。技だけでなく、曲もパラバルーンをより良いものにするための大切な構成要素の1つ。1つ目は、V6の『WAになって踊ろう』。保育士や保護者の方世代は一度はどこかで聞いたことがある曲ですよね。リズムが良く、ノリノリで演技をすることができるので、演技をする子供たちも観ている保護者の方も楽しめること間違いなしです!
友よ〜この先もずっと…
おすすめの曲の2つ目は、ケツメイシの『友よ〜この先もずっと…』。ダンスをはじめ運動会の曲としては欠かせないこの曲。友達を大切にしようという曲と友達と協力して行うパラバルーンの演技がマッチしますよ。子供たちの絆や成長した姿を保護者の方たちに伝えるのにぴったりですよ。
ツバメ
おすすめの曲の3つ目は、YOASOBI with ミドリーズの『ツバメ』。NHKの番組のテーマソングなので、この曲が好きな子供も多いのではないでしょうか。そのため、子供たちが楽しんで演技をすることができると思いますよ。
やってみよう
おすすめの曲の4つ目は、WANIMAの『やってみよう』。曲の題名からも分かるように、この曲はチャレンジを促すような曲。子供たちがパラバルーンに挑戦している姿と曲がマッチしていいですよね。またリズミカルな曲なので、パラバルーンの演目にはぴったりですよ。
ハルノヒ
おすすめの曲の5つ目は、あいみょんの『ハルノヒ』。クレヨンしんちゃんの映画の主題歌として有名になりましたね。そのため、曲を知っている子供たちも多いでしょう。子供たちが好きな曲で構成を作ると、子供たちのモチベーションアップをサポートすることができますよ。
パラバルーンを行う時に注意すること
安全確認
ここからはパラバルーンを行うときに注意することをお伝えします。パラバルーンを行うときに注意することの1つ目は安全確認。子供たちはパラバルーンを持って動くため、足元への注意力が下がります。そのため、転ぶリスクを下げるために、あらかじめ大きな石や枝などは除去しておきましょう。また、パラバルーンが風に煽られるのとともに、子供たちが怪我をしないように周囲のひらけた場所で行うと良いですよ。
並び方をあらかじめ決めておく

パラバルーンを行うときに注意することの2つ目は、並び方をあらかじめ決めておくこと。子供たちがどこに並ぶのかやパラバルーンのどの位置を持つのかで混乱や揉め事が起きないように、並び方はあらかじめ決めておきましょう。技によってはパラバルーンを上に持ち上げることもあるので、子供たちの身長を参考に並び方を決めるのがおすすめですよ。そして隣同士で大きな身長差が生まれないように並び方を決めましょう。並び方は子供たちと一緒に確認をして、スムーズに進めるようにしましょう。
技を詰め込みすぎない

パラバルーンを行うときに注意することの3つ目は、技を詰め込みすぎないということ。これは運動会や学芸会で披露するためのパラバルーンの技構成を考えるときに注意が必要です。技を詰め込みすぎると、子供たちの混乱を招き怪我につながります。そのため、応用的な技を詰め込むのではなく、基本動作を組み込んだり、行進で移動する時間を設けたりなどしましょう。子供たちが落ち着いて行えるような演技構成が大切ですよ。
まとめ
パラバルーンで体を動かすことの楽しさを知ってもらいましょう!
ここまでパラバルーンの紹介をしてきましたがいかがでしょうか。パラバルーンは子供たちが楽しめるだけでなく、協調性を育んだり、一体感の楽しさを学んでもらうなど良いところがたくさんあります。さらに、自分の頭に思い描いた動きを実際に体を動かして表現するので簡単な頭の体操にもなりますよ。運動会のお遊戯として、学芸会の演目としてパラバルーンを取り入れることも良いですし、保育園でのイベントとしてパラバルーンを行う時間を設けるのもおすすめですよ。ぜひ、パラバルーンを通して子供たちに体を動かすことの楽しさを知ってもらいましょう。
よくある質問
保育士くらぶにはどんな記事がありますか?
保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。
保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?
最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。
保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?
保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。