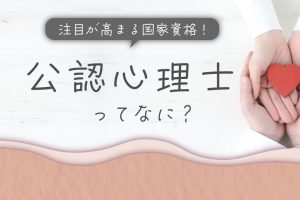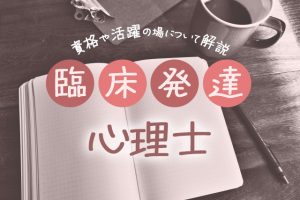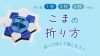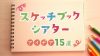目次
保育士・幼稚園教諭として日々お仕事を頑張っていらっしゃる皆様、こんにちは!
当サイト「保育士くらぶ」と、保育士・幼稚園教諭の方向けの日本最大級求人サイト「保育求人ガイド」を運営する弊社アスカグループは、専門のアドバイザーが多くの保育士・幼稚園教諭の方を対象に、20年以上にわたり転職・キャリアサポートを行っています。
保育士くらぶでは、保育士・幼稚園教諭の方にとって役立つ転職・キャリアノウハウ記事を配信しています。
保育士試験実技「言語」とは?
「言語に関する技術」は保育士試験実技の科目の1つです。
内容は、3歳児に3分間何もない状態でお話をするというもの。
お話の題材は4つの中から選ぶことができますが、台本などの持ち込みは出来ないので、お話の内容を自分の中でまとめて頭の中に入れておく必要があります。
今回はそんな保育士試験実技「言語表現」の合格のポイントを解説します。
2023年の各題材についての特徴などもまとめているので、是非参考にしてみて下さい。
「言語」の合格ポイント
手引きを確認する
言語表現で合格するために、まずは手引きに書かれている内容を把握しましょう!
- 子供は15人程度が自分の目の前にいることを想定する。
- 一般的なあらすじを通して、3歳の子供がお話を楽しめるように3分にまとめる
- お話の内容をイメージできるよう、適切な身振り手振りを加える
とあります。
また求められる力としては、
- 保育士として必要な基本的な声の出し方
- 表現上の技術
- 幼児に対する話し方
ができること、と記載されています。
注意点として
- 開始合図のあとに最初に題名を言う
- 絵本や道具(台本や人形)などの使用は一切禁止
- 3分間は退出出来ない
などが挙げられます。
これらは合格の最低条件ともいえるので、しっかり頭に入れておきましょう!
お話を選んでシナリオ作りをする
まずはお題の中からお話を決めましょう。
今年度のお題は
- ももたろう
- 3びきのこぶた
- 3びきのやぎのがらがらどん
- おおきなかぶ
です。
(それぞれのストーリーの特徴は後で詳しく解説します★)
決め方のコツとしては
- 自分が好きで楽しんでお話できるもの
- 語り分けが得意であれば登場人物が多いもの
を選ぶなど自分が自信を持ってお話しできそうなものを選択すると良いでしょう。
また登場人物が多いお話と少ないお話では工夫の仕方が違います。
多い場合はそれぞれのキャラクターによって声の使い方を分ける必要が出てくるので、演じ分が得意な人に向いているといえるでしょう。
登場人物が少ない場合は、声の使い分けは少ないですが、その分物語が単調になりがちなので、ナレーションで子どもたちを惹きつける必要が出てきます。
このような特徴にも注目して自分が堂々とお話ししやすい物語を選ぶようにすると良いですね!
お話を決めたら次はシナリオ作りをします。
手引きに記載されている通り、台本などの道具は使用禁止とされています。
そのため試験当日に向けて、シナリオをまとめて頭の中に入れておくことが大切になります。
お題になっている絵本などを丸暗記する必要はないので、まずはあらすじを理解して、それを3歳児が楽しめるように3分間にまとめたりアレンジしてみると良いですね!
シナリオ作りのポイントは
- 600〜800字を目安に3分間に収まるように作る
- 絵本などを参考に3歳児が理解できる言葉を使う
- 擬音語や繰り返しことば(ブーブー、ワンワン、ドコドコなど)を取り入れてみる
ことなどが挙げられます。
繰り返し練習
シナリオができたら後は練習あるのみです!
本番当日を意識して時間も測りながらシミュレーションしてみましょう。
本番はまず最初に題名を言うところから始まるので、練習でも言うようにすると良いですね。
練習を繰り返すうちに3分間という時間感覚も掴めるようになると思います。
また練習して慣れてきたら、身振りや手振りを加えて、クオリティを上げていくことも大切です。
実際に3分間自分がシミュレーションしている様子を誰かに見てもらったり、自分で動画を撮って見返したりするのも良いかもしれません。客観的に見ることで改善点なども発見しやすくなりますよ!
3歳児を想定した練習をしよう
手引きにもあるように、「3歳児の子ども」たちを想定することがとても重要です。
題材にもよりますが、絵本をそのまま読むと3歳の子どもたちにとっては理解が難しいことも多いです。シナリオを作る段階(アレンジする段階)で3歳の子でも理解できるようなわかりやすい話し方や表現を意識すると良いでしょう。
また話すスピードにも注意が必要です。話すペースが早いと、3歳の子どもたちは物語を理解することができずに、お話に飽きてしまうことが考えられます。
しかし、ただゆっくり話しても子供たちを惹きつけることは出来ません。
3歳の子供たちが物語に入りやすいスピードで、途中の内容によってテンポを変えるなどの工夫をしてみると良いですね!
人数を意識して練習する
こちらも手引きにも書かれていましたが、「こどもが15人程度いる」前でお話しすることが課題となっています。
練習も当日もこの人数を意識することが大切になります。
まず何よりも、声の音量が15人全員にしっかり聞こえる大きさでなければなりません。
そしてそれに加えて空間を意識することも大切です。
15人いるということは、子供たちは横にひろがっていたり、少し遠くにいる子がいる可能性があります。それを意識して目線を左右に配るなどの工夫が出来ると良いですね!
このような工夫は、試験当日にいきなりできることではないので、練習のときから意識してやってみるようにしましょう。
2023年の課題
ももたろう

誰でも知っている日本の昔話ですね。有名なので選びやすい題材ではありますが、いくつか気をつけたい点もあるので注意が必要です。
まず、ももたろうは比較的長さのある物語です。それを上手く自分で3分にまとめなけらばらないので、工夫が必要です。3分でまとめるために早口になってしまうと、子供たちに伝わり難いため、減点になってしまう可能性もあるので気をつけましょう。
話の要点や、子供たちが喜びそうな場面にスポットを当ててシナリオを作ってみるのがオススメです。
また、登場人物が多いのもこの物語の特徴です。おじいさん、おばあさんに始まり、犬やさるやキジ、さらに鬼など、沢山登場しますよね。
先ほども説明したとおり試験には絵本や道具は持ち込めません。つまりこの登場人物の演じ分けを、声色や身振りのみで表現しなければならないのです。
声を高くしたり低くしたり抑揚をつけてみたり、例えば犬のセリフであれば語尾にワンをつけてみるなど、工夫しながら演じ分けの練習をしてみましょう!
3びきのこぶた
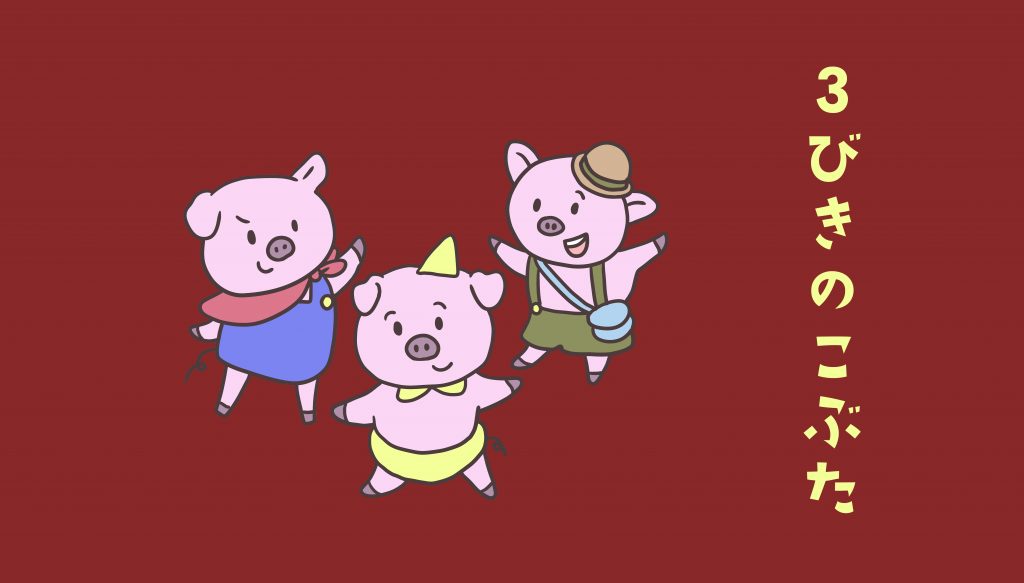
こちらは比較的短めのお話です。
早口になってしまうと時間が余ってしまう可能性が特に高いので気をつけましょう。
3分間に丁度よく収まるように時間感覚を意識すると良いですね。話すペースを工夫するのはもちろん、言葉と言葉の間を空けて話すというのもオススメです!
また3びきのこぶたのもう1つの特徴として、感情表現が必要になる場面が多いことが挙げられます。
例えばオオカミが来ることを子豚が怖がる場面では、身振りをつけつつ顔も不安な表情を浮かべて見ると良いでしょう。またオオカミに家を壊された場面では悲しいという感情が伝わるように顔や手を使って表現してみると良いですね。
お話が少し単調なので、こういった感情表現を大袈裟にやってみることで、物語に抑揚が出てくるかと思います♪
3びきのやぎのがらがらどん

ロシアの昔話である3びきのやぎのがらがらどん。
草を食べに山へ向かう途中、順番に橋を渡り川を渡ろうとする3びきのやぎですが、橋の下には恐ろしい化け物の「トロル」がいて襲い掛かろうとしてきます。
この物語は
- 恐ろしさ
- 迫力
を強く表現する必要がある物語といえるでしょう。
化けものトロルの恐ろしさや、それに立ち向かうやぎたちの勇敢さが子供たちに伝わるような話し方ができると良いですね!
がらがらどんの声の出し方や話の仕方を自分なりに工夫して、臨場感のあるお話をするとより雰囲気が伝わりそうです。
他の物語とは少し違って、怖い雰囲気や迫力がキーポイントになる3びきのやぎのがらがらどんですが、声の出し方などを工夫すればインパクトのあるお話ができそうです。
是非挑戦してみてはいかがでしょうか。
おおきなかぶ

有名なお話なので挑戦しやすい題材といえるかもしれません。
登場人物が多くて不安という人もいるかもしれませんが、会話などはそれほど多くなく、ナレーションで物語に抑揚をつけることが出来れば比較的お話しやすい内容になっています。
ナレーションで抑揚をつけるポイントとしては
「うんとこしょ どっこいしょ」の部分に注目してみるのがおすすめ。
この部分は大きなかぶを引っ張る人が増える場面でもあるので、言い方を変えてみたり声の出し方を変えてみると良いでしょう。
おおきなかぶは、お話の内容が繰り返しの部分も多く、単調にならないように注意が必要なので、このような工夫は必須といえるでしょう。
試験当日について
当日の服装について
当日の服装に特に決まりはありませんが、カジュアルすぎる服装であったり、清潔感に欠ける身なりだと試験管からのイメージも良くありません。
シンプルな服装で、髪型も表情がわかるスッキリとしたものにすると印象が良いかもしれませんね!
会場での流れ
会場へ行くと受験番号ごとに順番が書かれた紙などがもらえるので、その順番を待って試験に挑む流れとなります。
落ち着いて挑もう!
会場では自分の順番を待っているときに、前の受験者の声が聞こえてくることもあるようです。
特に自分と同じ題材が聞こえた場合には、自分と比べてしまって不安になってしまうかもしれませんが、「自分は自分」と割り切って練習してきたことを信じて堂々と試験に挑みましょう。
自信をもって物語を楽しもう!
保育士試験の実技の1つ言語について解説しました。
3分間という短い時間ですが、ポイントを抑えて自信を持って試験に挑めばきっと大丈夫です。
いろいろと気を付ける点はありますが、なによりも「子どもたちに楽しんでもらえるお話」ができるように自分自身も物語を楽しむことができると良いですね!
よくある質問
保育士くらぶにはどんな記事がありますか?
保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。
保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?
最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。
保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?
保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。