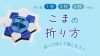保育士・幼稚園教諭として日々お仕事を頑張っていらっしゃる皆様、こんにちは!当サイト「保育士くらぶ」と、保育士・幼稚園教諭の方向けの日本最大級求人サイト「保育求人ガイド」を運営する弊社アスカグループは、専門のアドバイザーが多くの保育士・幼稚園教諭の方を対象に、20年以上にわたり転職・キャリアサポートを行っています。保育士くらぶでは、保育士・幼稚園教諭の方にとって役立つ転職・キャリアノウハウ記事を配信しています。
子供達が大好きな『雪遊び!』

雪遊びは子供達にとって楽しい自然遊びの一つ。大人になると雪の日は寒いし、通勤の時に煩わしく思うものでしょうが幼少期の頃を思い出してみると、雪はワクワクするものではなかったでしょうか。北海道ではすでに雪が降っており、24時間で積雪が50cm以上増えた所もあるそうです。地域によれば、雪が降るのが貴重な日になるところもあるでしょう。そんな冬の雪が降った時にしかできない貴重な遊びを心ゆくまま楽しみたいですよね。そこで今回は、子供達が大好きな「雪遊び」について以下の内容をまとめました!
- 雪遊びのねらい
- 雪遊びのための事前準備
- 保育でできる雪遊びのアイディア💡
- 怪我防止のために気をつけたいこと
「雪の日に何をしよう?」「子供たちが怪我をしないか心配…」とお悩みの方は必見です!是非最後までご覧になって、雪が降った時に子供達と楽しく遊べる計画を練ってみるのはいかがでしょうか。
雪遊びのねらい

体の発達にとても良い
雪遊びは実は体の発達にとても良いものなのです。雪はバランスが取るのが難しく、怪我をしやすくて気をつけないといけないところもありますがそれを長所に捉えると、バランス感覚を育つことができて、雪に応じた体の使い方を身につけることができるのです。
雪遊びは「感触遊び」の一つに分類される
雪の冷たさや触り心地に触れたり、雪を踏んだりすることは「感触遊び」の一つになります。感触遊びのねらいとして主に以下の4つがあります。
- 触る素材の感触を理解し、面白さに気が付く
- 大脳を刺激して五感(視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚)を養う事ができる
- 感触遊びに無我夢中になることで集中力が身につく
- 感触の変化を楽しむ事ができる
といったねらいがあります。
寒くても雪なら外遊びのやる気が!
普段、寒いと外に出るのが億劫になりなかなか外遊びをしようせず部屋の中で遊ぼうとする子供もいるかもしれません。しかし、そんな子供であっても雪の日になると外で遊びたがるかもしれません。そのくらい雪は子供にとって惹きつけるものがあるのです✨また、雪遊びはいつもよりカロリーを多く消費するので普段外で遊ぼうとしない子への運動不足解消に効果があります。
雪遊びをする前に準備したいこと

そりやおもちゃなどの道具を用意する
雪遊びで使うそりやおもちゃなどの道具を事前に用意しておきましょう。子供がおもちゃを使うときは誤飲に気をつけて。子供たちがおもちゃを取り合いになってしまうと大変なのでおもちゃは数も余裕をもって準備するようにしましょうね。
防寒対策を意識した格好を
服装・靴・帽子・雪に触れても大丈夫な手袋…などなど子供達が寒くないように防寒対策を意識した格好で雪遊びを行いましょう。雪で遊ばせるのが短時間であっても、そのままの服装では風邪をひいてしまうかもしれません。雪遊びをする際は、“事前に保護者の方に雪遊びをするので防寒ができ、雪でも安全な格好を用意すること”を伝えるようにしましょう。服装の選び方としては、スキーウェアだとゴワゴワしていて3歳以下の子供は逆に動きづらかったりします。撥水性のあるものを選ぶといいでしょう。4歳以上の子供は、セパレートタイプのいざという時にトイレや休憩時に着脱が簡単なものがおすすめです。
保育でできる!雪遊びの例❄️6選

❄️雪に触れてみる
まずは、雪に触れてみましょう!雪に慣れてない乳児の子達の中には雪に対して怖いという気持ちがある子もいるかもしれません。定番の遊びから入るのではなく手で触ってみたり、雪を踏んでみたりして楽しんで慣れていきましょう♪
❄️雪の手形
雪に手のひらを押し付けて、手型をつけてみても楽しいですよ。せっかくなので記念に写真を撮ってみるのもいいかもしれませんね。
❄️雪で物を作ってみる
お団子を作ってみたり、雪うさぎを作ってみたり、友達と協力して雪の山を作ってみたり…と色んなものを作ってみましょう!小さい手で雪を丸めてうまく作るのはなかなか難しいと思いますので最初は保育士さんがお手本を見せてあげましょう。
❄️かまくら作り
かまくらは雪が降ったときに作る定番のものですが、実はかまくらには2種類のかまくらがあるということをみなさんはご存知でしょうか?一つ目は、ドーム型のかまくら。そして、もう一つはブロック型のかまくらです。ドーム型は、雪を積み上げて山のようにして、その山の真ん中に穴を開けて洞窟のような形にします。もう一つのブロック型は、雪をブロック状に積み上げてドーム状に壁を作っていくのがブロック型です。子供たちと作るのは、ポピュラーで比較的簡単なドーム型がおすすめです。スコップやバケツを用意して子供達と協力して作ってみましょう。
❄️雪だるまを作る
雪だるまを作ることも雪遊びの定番ですよね☃️簡単な手のひらサイズから大きいものまで色んな雪だるまを作って遊んでみましょう!色をつけてみたり、身近に落ちてる木の棒や葉っぱなどをつけて顔を作ってみるとより雪だるまっぽさが増して楽しくなります。
❄️雪合戦
クラスのみんなで雪合戦してみてはいかがでしょうか。雪合戦はみんなでワイワイ楽しめるウィンタースポーツです。4歳以上の年中から行うのが最適です。異年齢クラスでもルールを設けることで楽しく遊ぶことができますよ。(※例えば、下の年齢の子たちにはハンデを与えるなど)
雪遊びをするときに気をつけること
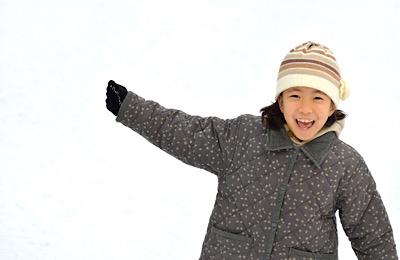
怪我に気をつけて遊ぶ
雪遊びは普段の外遊びに比べてより怪我をしやすいです。雪は大変滑りやすく、大人でも転倒してしまうものです。また、よく見ておかないと雪の中に岩やゴミなど埋まっている可能性もあります。そのため、保育士さんは十分な安全管理と子供達に対して事前指導が必要になるのです。
雪を食べないように
子供が誤って雪を食べないようにしましょう。遊んでる最中に雪が多少口の中に入ってしまうのは仕方ないですが、雪を直接食べないように事前に注意するようにしましょうね。雪は見た目は食べても無害に見えますが、実は大気中の塵やほこりが入っており、有害物質を多く含む酸性雪である可能性もあります。アメリカ疾病予防管理センターの「冬を安全に過ごすガイドライン」では「雪を食べると体温が下がるため食べないこと」と記載されています。雪を食べることは様々な害があり、危険だということを理解しておき、子供たちにも教えるようにしましょう。
脱水症状
脱水症状といえば暑くて汗をかきやすい夏に起こるものだと思われがちですが冬でも気をつけていないと遊んだ時に汗をかいて脱水症状になってしまうことがあります。脱水症状にならないためには、こまめな水分補給。そして、適度な休憩が大事なのです。子供の健康状態に常に配慮をして、思いっきり雪遊びを楽しめるように心掛けましょう。
まとめ
怪我に気をつけて楽しく遊ぼう!

雪に触れて遊ぶことはもちろんですが、1番は怪我をせずに楽しく遊べることを心がけることです!そのためには、防寒と安全のための格好と事前注意を忘れずに行いましょう!子供は元気で雪に興奮していて、休憩をとるのも嫌になるほど遊びたくて仕方なくなる子もいるかもしれません。しかし、怪我防止のためにも適度な休憩は必要なのです。雪は大人も滑りやすくなってるため、自分自身も怪我をしないように注意して子供達と遊びましょう!子供達にとって雪遊びがかけがえのない大切な体験になりますように✨
ᱸ☃︎❅本記事が役立ち、みなさんの保育士生活が豊かになれば幸いです。
最後までご覧いただき、まことにありがとうございました☃︎❅ᱸ
※本サイトは全国の保育園・幼稚園で働いてる人、これから保育士を目指す方への情報提供を目的としています。
掲載された情報をご利用いただいた結果、万一、ご利用者が何らかのトラブル、被害、損失、損害等が発生したとしても、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
室内で楽しめる!冬の手遊び・歌はこちらから⏬
よくある質問
保育士くらぶにはどんな記事がありますか?
保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。
保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?
最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。
保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?
保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。