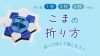目次
こんにちは!保育士くらぶ編集部です。保育士くらぶでは、保育現場で明日から使える最新トピックや保育士さんの転職、キャリアをサポートするコンテンツをお届けしています。求人情報や転職・キャリアのご相談は同グループが運営する「保育求人ガイド」をご覧ください。

いよいよ季節も寒くなってきて冬を感じますよね。今回はそんな冬の風物詩、「冬至の日」について意味や保育園での過ごし方について徹底紹介したいと思います。冬至の日に何をしようか迷っている方、過ごし方にお悩みの保育士さん必見です。ぜひ参考にしてみてくださね。
冬至とは?
冬至の意味
冬至(とうじ)とは、一言でいうと、1年の中で最も日が短い日のことです。つまり、明るい昼の時間が短く、暗い夜の時間の方が長い日のことを言います。基本的に日本では、寒くなるにつれて日照時間が短くなっていくイメージがありますよね。それが1年の中で最も起こるのが冬至の日なのです。なぜそのような現象になるかというと、地球の回転軸が傾き、地軸が公転面に対して太陽とは逆に向くためです。一方夏では、「夏至」と呼ばれる日があります。
2022年の冬至の日はいつ?
2022年の冬至の日は12月22日 (木) となっています。ちなみにこの日は毎年決まっているのではなく、年によって多少の変動が生じますが大体12月22日ごろです。昨年の2021年も12月22日でしたね。気になる年があれば、調べてみることをおすすめします!特に祝日になるわけではありませんが、日本では各家庭で冬至の日の風習を行うケースも多いかと思います。下記では、そんな冬至の日の風習について紹介していきます。
冬至の日の風習
かぼちゃを食べる

冬至の日にはかぼちゃを食べる風習があります。かぼちゃは栄養価が豊富な食材として冬に引き起こしやすい風邪や病気の予防に効果的だったとされ、この日に食べられるようになりました。また、かぼちゃは本来、夏によく獲れて食べられるものですが、長期保存が効くということで冬至に食べることがベストだと考えられたわけです。かぼちゃは、煮物にしたり、スープに入れたりなど様々な料理の中に取り入れて食べられることが多いです。冬至の日に限らず、冬の間はかぼちゃを食べて力をつけることも良いですね。かぼちゃが苦手な子どももいるかと思うので、苦手克服のチャンスに使うことも手だと思います!
ゆず湯に入る

冬至の日に行う風習として代表的な一つに、ゆず風呂に入るということがあります。自分が入るお風呂に、ゆず本体をそのまま入れます。ゆずの皮は、結構改善を促す他、風邪予防に効果的なビタミンCが豊富に含まれており、冬の寒い季節にはぴったりでした。また、ゆずの強い香りは、邪気が起こらないとされていることや、ゆずが実るまでに時間がかかることから長年の苦労が実るよう願いが込められているなど縁起の良い果実として冬至の日の定番となっています。ゆずをお風呂に入れる際には、そのままではなくネットや桶にいれる人も多いと思います。また、ゆずがない場合は、ゆずの香りの入浴剤などで入るといいかもしれませんね。
冬至粥を食べる

世間的には有名ではないかもしれませんが、冬至粥というものがあります。別名で、「小豆粥」ともいわれる冬至の日に食べるお粥のことです。冬至粥は、小豆を入れることが一般的ですが、かぼちゃを入れたりなど他の食材を入れてもおいしく食べることが出来ます。小豆を入れる理由としては、小豆のような真っ赤な色には邪気を払う力があり、縁起がいいものとされているためです。そうした小豆を冬至の日に食べることで邪気を払い、運気を入れるという意味が込められていたとのことです。いわゆる魔除けとして非常に優れた食べ物なのですね。新年を迎える前ということもあり、行っておきたい風習の一つです。
保育園での冬至の日の過ごし方
子どもたちに冬至について説明する
冬至について知らない子どももまだまだ多いのではないでしょうか。日本の伝統である冬至について子どもたちに由来や風習を教えることもとても大切です。子どもたちに集まってもらい、「今日は何の日でしょうか!」などクイズ形式にしても楽しいかもしれません。「お風呂にゆずを入れて入ったことがある人!」など子どもたちの経験をもとにして教えていくのもおすすめです。
「ん」が付く食べ物探し
実は、冬至の日には「ん」が付く食べ物を食べるという風習もあります。「ん」には「運」がかけられており、縁起がいいとされていました。そのため冬至の日には、運気が来るという意味の「ん」の付く食べ物を食べることが良いとされていた説があります。他にも、いろはにほへとが最後に「ん」で終わることから、新年に向け縁起のいい意味合いがあった説もあります。こうした「ん」が最後につく食べ物を子どもたちと探すことで、冬至の日の風習を体感しましょう。例えば、「うどん」「みかん」「かんてん」「だいこん」などがありますね。誰が一番多く探せるか、探した中で一番おいしそうなものを決めるなど工夫して楽しめるとよさそうです。
冬の手遊び歌で遊ぶ
冬至は、日が短いということもあり1年の中で最も冬を感じる日でもあります。そのため、これから本格的に寒くなる真冬に向け、手遊びなど季節感のある遊びをしてみることがおすすめです。歌や手遊びは、体をほぐす効果もあり、寒い冬にはぴったりです。
保育士くらぶでは、冬に遊べる手遊び歌や歌に関する記事を動画付きで出しています。明日からでもすぐ実践できる内容となっていますので、是非ご覧ください♪
ゆず湯を体感する
上記で書いたように、ゆず湯は冬至の日の伝統的な風習です。園においても、足湯や手だけ浸かるなど工夫次第では子どもたちがゆず湯を体験することが出来ます。バケツや洗面器、夏の間に使用するプールなどを利用して簡単なゆず湯体験コーナーを作ってみると面白いかもしれません。ゆず湯を通して日本の伝統に触れるだけでなく心も体マあったまることが出来ますね。
冬の折り紙を作って遊ぶ
冬至ということで冬らしい折り紙を作って遊ぶこともおすすめです。室内で遊べるということもあって寒さしのぎにももってこいですね。冬至の日には、ゆずやかぼちゃなど冬至にちなんだ折り紙で遊んでみるのもおすすめです。
☆ ゆずにゃんこ
☆ かぼちゃ
子供達へ冬至を伝える時のポイント
紙芝居やペープサートを使う
紙芝居やペープサートといった登場人物が出てくる製作物は子供達の興味をひきやすくとてもおすすめです。その際、保育士さんたちで物語などのストーリーを考えてみるのも楽しいかもしれませんね。子供達が楽しみながら冬至について学べるだけでなく、より具体的に想像を働かせることも出来るようになります。
▽ 保育士くらぶが過去にあげている関連記事です。作り方や活用法まで幅広く紹介しているので是非参照してみてください♪
わかりやすい言葉で言い換える
子供達に説明する際にはわかりやすい言葉で話す必要がありますよね。特に、「冬至」などの伝統用語は難しく理解し難い言葉遣いも多いので、わかりやすく言い換えましょう。例えば、「冬至の日っていうのはね、1年の中で1番冬を感じる日なんだよ。」「今日は、悪いものを追い払うためにゆずが入ったお風呂に入ったりかぼちゃを食べると良い日なんだよ。」「今日は、1年の中で1番大洋さんが出ている時間が少ないんだって。」など、かみ砕いた言い回しにすることが大切です。
日本の伝統「冬至」を体感しよう

冬至の日について紹介していきましたがいかがでしたか?意外と大人でも知らないような由来や風習があり、趣がありますよね。子どもたちはまだまだ幼いですが、そうした日本の伝統を知り体感することで知識や興味関心が深まるためとても大切なことです。冬至の日は、家庭だけでなく保育園でも冬至らしさを体感できるように工夫していきましょう。
よくある質問
保育士くらぶにはどんな記事がありますか?
保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。
保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?
最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。
保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?
保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。