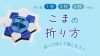目次
6月のおたよりの準備はできましたか?6月といえば梅雨の時期です。皆さんは梅雨といえばどんなイメージを思い浮かべますか。雨が鬱陶しかったり、ジメジメしていて憂鬱だったりしてあまり好きではないという方も多いのではないでしょうか。梅雨はジメジメとしていて気分が落ち込みやすい日が続きますね。こんな日にこそ梅雨の憂鬱な気持ちを吹き飛ばして見た人の気分が晴れるようなおたよりを書いてみてはいかがでしょうか。今回は、6月のおたよりの文例やおたよりのポイントなどをご紹介します。
6月のおたより文章例【書き出しと挨拶】
書き出しと挨拶の文例
時候の挨拶を添えながら、子どもの園での様子についての書き出しの文です。子どもたちが今月は園内でどんな様子なのかが書き出しからわかる文ですね。
6月のおたより文章例【季節感がある文】
文例①
おたよりには、保護者へ伝えたい連絡事項を書いてもOKです。季節感もあり、子ども達が身につけている雨具についての注意喚起ができる文例です。
文例②
こちらも雨具について注意喚起ができる文例です。子ども達の傘の取り扱いには大変注意深く見守らなければなりません。保護者の方にもおたよりで伝えておくことで子ども達の怪我の防止につながります。
6月のおたより文章例【子どもの年齢別】
【乳児】0歳児から2歳児クラス
乳児の子どもたちはまだまだ雨に慣れてない子どもが多いです。乳児クラスの保育士さんは、そんな子どもたちの様子を活かしたおたよりを書いてみてはいかがでしょうか。
【年少】3歳児クラス
6月に入ると新年度から3ヶ月が経ちますね。そろそろ環境の変化に馴染む子どもも多くなります。3歳になると、お友達と自然に遊ぶ様子が見受けられますよ。そんな子どもたちの様子を現した文例です。
【年中】4歳児クラス
季節の挨拶を添えながら、子どもの様子を伝えています。4歳ごろから少しずつルールを守って遊べるようになります。そんな子どもたちの様子をおたよりに書いてみてはいかがでしょうか。
【年長】5歳から6歳児クラス
5歳から6歳児クラスは一番上のお兄さんお姉さんのクラスです。子どもたちがお兄さんお姉さんになった姿をおたよりを通じて保護者の方々に積極的に伝えてみましょう。
6月のおたより文例集【行事やイベント関連】
文例①父の日についてのおたよりの文例
父の日に向けた文例です。おたよりを見た保護者の方々が笑顔になるように心を込めて書きましょう。
文例②虫歯予防デーについてのおたよりの文例
6月の虫歯予防デーについて紹介している文例です。子どもの虫歯予防について保護者の方に注意喚起もできる良い文例ですね。
文例③夏至の日についてのおたよりの文例
夏至の日にちなんだ文例。夏至の日について紹介しながら、保護者の方に注意を促すことができる文章ですね。
6月のおたより文例集【健康関連】
文例①コロナウイルスについてのおたよりの文例
6月もより一層健康対策に注意しながらも、継続して子どもたちが安心安全に過ごせる園作りに取り組んで参りたいと思います。ご家庭でも早寝早起きや食生活を心掛け、体調管理にはより一層注意しましょう。
6月もより一層健康対策に注意しながらも、継続して子どもたちが安心安全に過ごせる園作りに取り組んで参りたいと思います。
子どもたちが安心して登園できるように園での取り組みを記載しています。園の感染症対策についての記載があると、子どもたちが安心して通える園であると実感できる文章になりますね。
文例②コロナと食中毒についてのおたよりの文例
6月はウイルスが発生しやすい環境になるので、対策にますます力を入れていきたいと思いますので引き続きご家庭でも手洗い・うがいなどの対策の方をよろしくお願いします。
新型コロナウイルスについて触れながら、食中毒についても記載しています。ご家庭でもウイルス対策に気をつけるように書いておくとより注意喚起ができて良い文章になりますね。
6月の保護者の方へのおしらせの文例
衣替えについての文例
6月に入り、これから本格的な夏を迎えます。衣替えについてお願いする文章を書いてみるのもいいかもしれません。名前の記入についても一緒にお願いすると記入漏れを防ぐ効果があり、とても良いでしょう。
6月に書くおたよりのポイント
行事を取り入れる

6月の行事といえば、毎年6月の第3日曜日と定められている父の日。2022年の父の日は6月19日の日曜日に実施されます。父の日のことをおたよりに書くと子どもたちのお父さん方が喜ぶこと間違いなしです。また、6月4日から6月10日には虫歯予防デーという歯と口の健康を意識する行事もあります。行事に関連して保育園や幼稚園で行う活動について書くと保護者の方が子どもが園で何をしているか把握することができますよ。
梅雨

6月といえば梅雨の季節です。そんな梅雨の季節を活かした文を書いて季節感が出るおたよりを書いてみるのはいかがでしょうか。また、梅雨の時期は外での遊びがしづらくなる時期でもあります。そのため、子ども達は室内で楽しく遊んでいる様子を文に書いてみるのも良いかもしれませんね。梅雨の時期は煩わしいですが、どんよりした梅雨の日の空気を吹き飛ばすようなおたよりをかけると良いですね。
コロナや食中毒など健康関連

まだまだ世間ではまだコロナウイルスが猛威を奮っています。注意喚起の意味でもおたよりにコロナウイルス関連を載せてみてもいいかもしれません。また、6月はコロナウイルスだけでなく食中毒に関しても注意する必要があります。お弁当がある園では子どもが食中毒にならないよう、保護者の方へ向けてお弁当を作るときに十分注意するよう促す文章を入れると食中毒の予防に繋がりますよ。給食の場合でも園での食中毒への対策の取り組みや予防法などについても記載すると保護者の方の安心感につながるのでおすすめです。
文章の基礎を理解して書く
文の基礎を理解できてないと、うまく文を書くことができません。5W1Hを意識してみるようにしましょう。5W1Hとは以下の6点のことです。
- When いつ
- Who だれが
- Where どこで
- What なにを
- Why なぜ
- How どのように
この5W1Hを意識する事で、相手に伝わりやすい文章を書くことができ、伝えたい情報を整理できますよ。文章の基本的なことなのでぜひ意識して書いてみましょう。
一文は80文字以内
一文を80文字以内で書くことはおたよりだけでなく、文章を書く上で基本的なことです。文章を書くのが苦手な人は、うまく言い切れずに歯切れがなく文が長くなってしまう傾向があります。文が長ければ長いほど読み手は前半部分が理解できずに文がわかりにくいものになってしまうので気をつけましょう。それに伴い、読み返す時間も長くなり、読み手にストレスがかかってしまう原因にもなるのです。おたよりの文章は無理して長くする必要はありません。一文の目安は長くても80文字以内にするように意識して書いてみましょう。
読み手にストレスを感じさせない文章を
読み手にストレスを感じさせないような文章を書くようにしましょう。どうしたら読み手に理解してもらえるのか、どんな言葉を使ったら良いかを考えて書いてみましょう。おたよりは無理に難しい言葉を使わなくてOKです。また、似た表現を使いすぎてしまうことも文章が読みづらくなってしまい読み手にストレスがかかります。どうしても似た表現になってしまう時は類語を調べて言い回しを変えてみましょう。類語を調べる時は類語辞典がおすすめです。読み手に苦労をかけない文章を心がけましょうね。
6月のおたよりにおすすめなイラスト
梅雨のイラストや父の日のイラストがおすすめ
6月といえば梅雨をイメージしますよね。梅雨を連想させるカエルや傘、てるてる坊主、かたつむりなどのイラストを添えてみてはいかがでしょうか。また、6月には父の日もあります。父の日といえば、黄色いバラやお父さんの顔などのイラストが多く思い浮かびますよね。「お父さんありがとう」といった言葉が書いているイラストもおすすめですよ。行事系のイラストの探し方は「行事の名前+イラスト」と検索することでたくさんイラストが出てきますのでぜひ検索して使ってみてください。
まとめ
雨でどんよりした空気を吹き飛ばすおたよりを作ろう
今回は、6月のおたよりについてまとめてみました。いかがでしたでしょうか。梅雨の時期は室内で遊ぶことが多くなります。6月は子どもが室内でも楽しんでいる姿を伝えると雨の日でも子ども達が楽しんでいる様子が保護者の方に伝わりますよ。ぜひ室内での生活に着目しておたよりを作ってみてはいかがでしょうか。本記事を参考にして、見た人の気分が晴れるようなおたよりを作ってみてくださいね。
※本サイトは全国の保育園・幼稚園で働いてる人、これから保育士を目指す方への情報提供を目的としています。
掲載された情報をご利用いただいた結果、万一、ご利用者が何らかのトラブル、被害、損失、損害等が発生したとしても、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
よくある質問
保育士くらぶにはどんな記事がありますか?
保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。
保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?
最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。
保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?
保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。