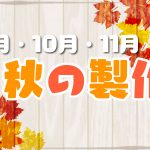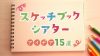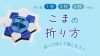目次
トンボ製作をぜひ子どもたちと一緒に行ってみてはいかがでしょうか。製作は子どもたちが楽しめるだけでなく安全面にも配慮して行う必要があります。発達状況によっては子どもたちはまだ器用にハサミなどの道具がうまく使えない子どもも多いです。そのため、製作の仕方に工夫をしなければいけません。では、どのように製作を行うと子どもたちみんなが安心して楽しめるのでしょうか。今回は年齢別におすすめのとんぼ製作をご紹介します!
0歳~1歳児におすすめのトンボ製作
ひらひらトンボ
【用意するもの】ラップの芯・画用紙・スズランテープ(30cmx2本)・セロハンテープ
1色画用紙一枚とラップの芯一本を用意します
2ラップの芯を画用紙で巻いてテープでとめる
3スズランテープ30cm二本を用意します
4画用紙に結びテープでとめる
5トンボの目を描く
6描いたトンボの目を(4)に付けたら出来上がり!
工程が少ないので0歳~1歳の子どもでも簡単に製作を行うことができますよ。”
2歳児におすすめのトンボ製作
赤とんぼ
【用意するもの】折り紙 トイレットペーパーの芯 トンボの羽二つ トンボの目二つ のり マジックペン
1トイレットペーパーの芯を折り紙にはります
2トンボの羽を重ねてトイレットペーパーの芯にはります
3トンボの目を描きます
4トイレットペーパーの芯に(3)の目をはったら出来上がりです!
刃物を使わず簡単にできるので2歳児でも楽に製作ができますね。動かして空に飛ばしてぜひあそんでみてくださいね。”
【年少】3歳児におすすめのトンボ製作
トンボモビール
【用意するもの】トイレットペーパーの芯・PEテープ・紐・割り箸・毛糸・画用紙・テープ
1トイレットペーパーの芯に画用紙を巻きつけます。
2PEテープを2本巻きます。
3トンボの目をつけます。
4割り箸とトンボに毛糸を結んで固定すれば完成!
割り箸に関してはあらかじめコーティングしておくことで箸がボロボロになってしまっても指に木屑が刺さってしまうことが減り、怪我の防止につながります。コーティングするときは、マスキングテープやビニールテープなどを使うことをおススメします。”
【年中】4歳児におすすめのトンボ製作
竹とんぼ
【用意するもの】紙コップ・ストロー・はさみ・キリ・テープ
1紙コップの縁をはさみで切ります。
2紙コップの縁から底に向かって6等分にカットします。
※このとき切り込みと底の感覚を5mmほど開けましょう。
3紙コップの羽を斜めに折ります。
4羽の中央にキリで穴をあけます。
5ストローをカットします。
6ストローにはさみで切り込みを入れて、開きます。
7(4)で開けた穴にストローを差し込み、テープで固定します。
8最後にペンで絵をかいたら完成!”
デカルコマニーでトンボ製作
デカルコマニーという芸術技法を使い、トンボを描いてみるのも面白いですよ。デカルコマニーとは、フランス語で転写することを意味する芸術技法のことです。デカルコマニーという名前だけ聞くと一見難しそうだと感じるかもしれません。しかし、デカルコマニーは小さな子どもでも問題なく幅広い年齢で楽しむことができますよ。デカルコマニーで用意するのは、画用紙・絵の具・筆のみです。絵の具用のパレットを用意するのもいいですが、画用紙に直接絵の具を出して描いていってもOKです。ただし、乳児の子どもは特に絵の具を飲み込まないように気をつけましょう。”
【年長】5歳~6歳児におすすめのトンボ製作
トイレットペーパーの芯でトンボ
【用意するもの】クリアファイル 茶色い折り紙 筒の廃材 はさみ のり シール セロハンテープ ペン
1つつに茶色のおりがみをまく
2クリアファイルに羽の形を描いてはさみで切る
3カットした羽にシールを貼ったりペンで模様を描く
4デザインした羽の先を内側に少しだけ折り曲げる
5折り曲げた部分をつつの側面に沿わせるようにしてテープで羽を付ける
6最後にシールでトンボの目をつける
7トンボの出来上がりです
トンボの折り紙
1まずは、折り紙2枚・のり・ハサミ・目を描いたシールを用意しましょう。
2体を作っていきます。折りすじをつけて半分に切る
3半分に折る
4さらに半分に折る
5横に半分に折る
6羽を作っていきます。折り筋ををつけて1/4に切る
7さらに折り筋をつける
8真ん中に少しすき間をあけて上と下の角を折る
94つの角を少し山折りする
10(4)の内側にノリをつけて(8)をはさむ
11シールを目の位置に貼ったらトンボの出来上がり!”
トンボ製作の指導案の書き方
文章表現の仕方
指導案を書くときは基本的な文書のルールや表現の仕方にも注意する必要があります。文章のルールや表現の仕方の例は以下の通りです。参考にして文章を組み立ててみましょう。
・語尾の文末表現をだ・である調やです・ます調で統一すること
・主語がぶれないようにすること
・「子どもと◯◯をしてあげる」といった上から目線な表現を使わないこと
・誤字脱字がないようにすること”
ねらいの書き方
指導案の書き方では、ねらいの部分が難しいという人が多くて書くのに苦戦するようです。ねらいの書き方は、活動内容やその日の流れを先に記入して、その中からその日のねらいを探すと分かりやすいかもしれませんよ。 遊びのねらいの書き方は「遊びの名前+ねらい」で検索すると分かりやすいですよ。トンボ製作のねらいで苦戦している方は、次の章でねらいについて解説していますのでぜひこちらを参考にしてみてくださいね。
トンボ製作のねらいは?
想像力が養う

想像力とは、目には見えないものを思い浮かべる力のことを言います。想像力を掻き立てながら製作をしていくのもねらいの一つですよ。製作遊びは、型に囚われずに自分が好きにイメージをして、どんどん頭の中で自分が作りたいものを膨らませながら楽しむことができます。そのため、完成図を頭に描いて製作を行うことで想像力が養われますよ。想像力は大人になってからも様々な場所で発揮ができます。ぜひ幼少期に身につけたい能力ですね。
達成感を感じることができる
子どもは完成図を頭で描き、時には失敗しながらも製作物を完成させることで達成感を得ることができます。子どもたちにとっては製作物が完成したという些細な成功体験でもこれから生きていくうちに必要なことです。成功体験があることで自信を持って生きられるようになりますよ。子どもの「できた!」という声が聞こえたときはぜひ褒めてあげてくださいね。一緒にできた喜びを分かち合うことで子どもはさらに製作に対しての意欲ややる気が出ることでしょう。
手先が器用になる

製作遊びは遊びながら自然と手先を動かす訓練ができます。最初は、保育士さんの手の動きをみながらどのように手を動かしているか見様見真似で子どもは真似をします。初めはぎこちない子どもたちですが、慣れていく上手に製作することが出来るようになりますよ。道具の使い方や色について理解し、子どもたちはどんどん器用になり自由に色んなものを作り、製作の幅が広がるかもしれませんね。
感覚や感触を楽しむ

子どもは発達段階によって手で何かを握ったり動かしたりすることも出来るようになります。製作には、紙を折ったりハサミで切ったりのりで貼ったりといったいろんな作業がありますよね。子どもたちにとって製作は手で何かを掴むことにより感覚や感触を得ることが出来るものです。幼少期の子どもは積極的にいろいろなものに触れてみることはとても大切。子どもたちがものを触って楽しめるだけでなく、発育効果に期待できるのです。
トンボ製作を行う時のポイント
安全に作業を行える環境を

子どもたちが安心して製作を行える環境を整えましょう。子どもはやっていいこととやってダメなことの区別がついていません。刃物類は特に0歳から2歳ごろの乳児が扱うのは難しく、危険を伴います。子どもが使って安全な道具を使うようにしましょう。子どもたちが製作中に起こりうる怪我や事故の例を出すと、絵の具に誤って口を入れたり、ハサミで指を切ってしまったといったことが挙げられます。こういった怪我や事故がないように保育士さんは、事前準備や製作中の子どもたちの見回りがとても大切になっていきます。
手遊びうたでトンボ製作の導入をしよう!
手遊びうたでトンボについて興味を持たせてから製作に入るのもおすすめですよ。手遊び歌は、活動前後の切り替えや、園児をまとめたいとき、注目を集めたいとき、活動の導入としての役割があります。手遊び歌のねらいは、大人と子どもが適切なスキンシップやコミュニケーションをとることや手を動かすことで脳の発達を促してリズム感を養うことなどがあげられます。ぜひ手遊びうたでまずは導入してみてはいかがでしょうか。”
年齢に合わせた製作をする

本記事でも年齢別に取り上げたように、製作にはそれぞれ適した年齢の遊びがあります。年齢や各個人のレベルに合っていない製作に取り組むと、簡単に感じる子がいたり、難しく感じる子がいたりと子どもによって製作の難易度はバラバラなのです。年齢やレベルに合わせないと子どもたち全員が平等に製作を楽しむことが出来ません。また、発育効果が薄れてしまうデメリットもあります。難しそうであれば、保育士さんでやってあげることや声をかけてアドバイスをするといったことをして、製作において不便に感じる子どもがいないようにしましょう。
まとめ
製作で秋を盛り上げよう!
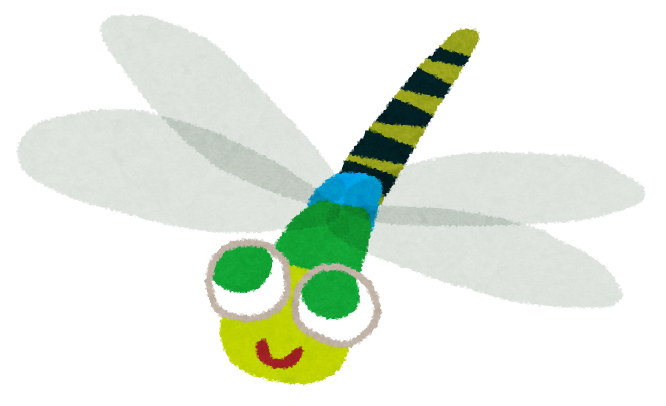
今回はトンボ製作のアイディアやねらい、指導案の書き方、製作のポイントについてまとめてみました。いかがでしたでしょうか。製作は、季節に合ったものを行うことで子どもたちが四季や文化を学ぶきっかけになります。そのため、秋によくみられるトンボを作ることで季節感を感じて、子どもたちがこれから生きていく上で大切な感性が磨かれるでしょう。今回ご紹介した動画ややり方を参考に怪我に気をつけて子どもたちと楽しくトンボ製作ができるといいですね。
※本サイトは全国の保育園・幼稚園で働いてる人、これから保育士を目指す方への情報提供を目的としています。掲載された情報をご利用いただいた結果、万一、ご利用者が何らかのトラブル、被害、損失、損害等が発生したとしても、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
よくある質問
保育士くらぶにはどんな記事がありますか?
保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。
保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?
最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。
保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?
保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。