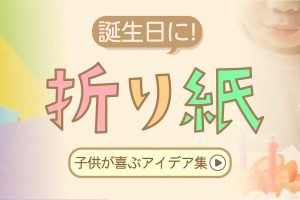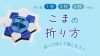目次
こんにちは!
保育士くらぶ編集部です。
保育士くらぶでは、保育現場で明日から使える最新トピックや保育士さんの転職、キャリアをサポートするコンテンツをおとどけしています。
求人情報や転職・キャリアのご相談は同グループが運営する「保育求人ガイド」をご覧ください。
はじめに
虫歯予防デーとは?

いよいよ本格的な梅雨となる6月ですね!
そんな6月には、「虫歯予防デー」という歯と口の健康を意識する期間があります。
虫歯予防デーは、一般的に、6月4日~10日とされていますが、室内で過ごす期間が増える6月は、1か月間丸々歯を意識する期間としてもいいかもしれません。特に、緊急事態宣言の影響で室内で過ごす機会も増え、おやつや甘いものをより食べる子どもが増えているかと思います。園でも家庭でも、いつも以上に子どもたちの歯を気にかける必要があります。
関連記事でもっと知る
虫歯予防デーの目的
園全体で虫歯予防に関する指導を行うことで、子どもたちも歯の大切さを実感し、日頃から歯の健康を心掛けるようになります。主な目的とメリットは以下の通りです。
☑ 歯の大切さに気付くことが出来る
☑ 正しい歯磨きを知ることが出来る
☑ 規則正しい歯磨きの習慣がつく
☑ 虫歯の怖さを学ぶことが出来る
関連記事でもっと知る
〔虫歯予防デー〕保育園での取り組みについて
保育園では具体的にどのような取り組みが行われているでしょうか。例文を交えながら紹介しているので、是非参考にしてみてください。
簡単な言葉への言いかえ

まだ幼い子供たちに虫歯予防デーについて説明をすることは難しく、なかなか理解してもらいにくいかもしれません。そんな時、重要となってくるのが、「簡単な言葉にする」ことです。
以下、園児との会話における例文です。
A「みんなの口の中が元気でいられるように、ピカピカにすることだよ。」
Q「虫歯予防デーって何をするの?」
A「みんなのお口の中や歯をピカピカにして、虫歯にならないようにするんだよ。」
A2「みんなで歯磨きの仕方を勉強して、正しく丁寧に磨けるようにするよ。」
Q「虫歯になったらどうなるの?」
A「お口の中が、痛い痛いになっちゃうんだよ。」
A「歯の病院に行って、治してもらわないといけないんだよ。」
出し物や劇
ここでは実際に、身体、道具などを使って表現する方法について紹介します。園児たちからすると、視覚聴覚の両面から口内の重要性について理解することが出来るので、非常におすすめな方法です。
やり方も準備も簡単なため、参考にしやすいかと思います。
① クイズの出し合い
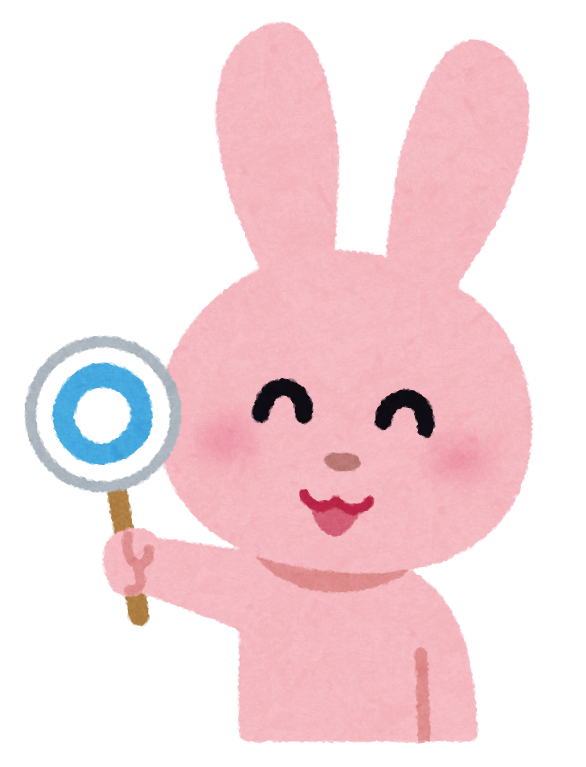
先生「甘いものばかりを飲んだり食べていると虫歯になりやすい。〇か×かどっちでしょう?
子ども「〇!」
先生「虫歯ができやすいのはどんな時でしょう?1、起きた時 2、寝ている時」
子ども「1?」「2!」※答えは2
☑ 子どもたち同士で出し合う
子ども1「この中で何を食べたら虫歯になりやすいでしょう?1、チョコレート 2、コーラ、3、おせんべい」
子ども2「1と2!」
子ども同士で、クイズを出し合うと記憶にも残りやすく双方の子どもにメリットが生まれます。交互に出し合うなど工夫をしていきましょう。
② 先生の劇

☑ 舞台や教室などで子どもたちに鑑賞してもらう
現在は、コロナによる影響で大勢で集まるイベントは出来ないかと思いますが、先生の劇を録画したものを流したり、感染対策を万全に行いながら少人数で実施をしたりなど工夫をしてみることがおすすめです。
子どもたちにとってかけがえのない大好きな先生たちが、虫歯によって攻撃され、弱る姿を見れば、歯の健康に敏感になり、具体的なイメージが湧きやすかもしれませんね。
絵本の読み聞かせ

日頃、園でも家庭でも行われている「絵本の読み聞かせ」ですが、歯に関する絵本を取り上げるのも1つの方法です。
「歯磨きの仕方」や、「虫歯予防デー」「虫歯になると」といった歯に関するテーマを取り上げた絵本を読むことがおすすめです。その際、具体的にイメージしやすい絵や写真が大きく載っているものを選ぶように心がけましょう。
読み聞かせでは、擬音語や大切な部分に抑揚をつけて話をすると子どもたちの記憶に残りやすいかと思います。
ペープサート

ペープサートとは、幼児向けの紙人形劇のことを指します。保育園や幼児の現場ではよく使用されているかと思います。
ペープサートでは、「歯」に関する劇をパロディ風に行うことができ、園児たちの印象に残りやすく非常におすすめな方法です。様々な歯のイラストを描き、楽しみながら学びましょう。また、子どもたちと製作から共にすることで、興味や関心を引き、より濃い学びにすることが出来ます。
☆ 準備するもの
☑ 割りばし、ストロー
☑ マジックペン
☑ 色鉛筆やクレヨン、絵具
☑ はさみ
☑ のり、セロハンテープ
保育士くらぶでは、ペープサートに関して詳細を記事にしているので、是非参考にしてみてください。
歯磨きの歌
歯磨きに関する歌を歌うことで、子どもたちに歯磨きの大切さや方法を教えていきましょう。
☑ 先生の後に続いて歌う
☑ リズム歌を作り、子どもたちと歌う
☑ 先生のピアノで歌う
☑ 歌の歌詞付きの絵本に沿って歌う
歌を歌うことで、リズム感覚で覚えることが出来るため、効率よく歯磨きを習慣化することが出来ます。
園でも家庭でも気を付けるべき歯の習慣
上記では、歯の大切さを教える方法について示してきましたが、ここからは実際に日常で気を付けてもらいたい習慣について紹介していきます。園でも家庭でも実践することで、子どもたちにとって習慣化します。
食生活習慣

何を口にするかによって、口内の健康状態が変わるため、飲食物には非常に注意する必要があります。
下記には、虫歯になりやすい代表的な食べ物を挙げてみました。保育園などで出す間食や、家庭で保護者が与える飲食物に下記の物が多く含まれていないかよく確認しましょう。
☆ 歯に良くない(虫歯になりやすい)飲食物
☑ コーラなどの炭酸飲料
☑ キャラメル
☑ スナック菓子
☑ 柑橘類
☑ 堅いクッキー
たまに食べたり飲んだりすることは良いですが、頻度が多かったり、すぐに歯磨きをしないと虫歯になりやすく口内環境に支障が出てきます。与える際はきちんと調整し、食べたあとは歯磨きやうがいを促しましょう。
歯磨きのタイミング
歯磨きをするタイミングも非常に重要です。目安として、1日少なくとも2~3回歯磨くように意識しましょう。
下記は、あくまで目安なので参考程度としてください。
☆ 歯磨きのタイミング(目安)
☑ 昼食後
☑ 朝磨けなかった場合は登園後の空いている時間
☑ 間食後
☑ 夕食後、寝る前
園内で歯磨きをするためにも、歯ブラシセットの持参を保護者側に促す、園でも使い捨て歯ブラシや紙コップを用意するなど準備が必要となってきます。
正しいブラッシング

歯磨きは、やり方次第で無意味なものになってしまいます。正しい歯磨きを身につけさせ、虫歯のリスクを減らしていきましょう。
☆ 正しいブラッシングのやり方
② 歯と歯茎の間に45度にあてて磨く
③ 小刻みに動かす
④ 軽い力でシャカシャカと(ペンを持つくらい)
⑤ 歯は、1~2本感覚で磨く
「食べたら磨く」ということを習慣化させることがポイントです。そのためにも、園と家庭の双方で歯磨きを当たり前の行為にしていかなければなりませんね。
仕上げのブラッシング

子どもたちのブラッシングが終わったら、大人がチェックをしてあげることが大切です。
仕上げのブラッシングでは、単に2周目の歯磨きを行うのではなく、磨き残しを見つけ入念に磨いていく事が重要となってきます。下記では、主に汚れがたまりやすいところをまとめました。
☆ 汚れ(歯垢)がたまりやすいところ
☑ 歯と歯茎の境目
☑ 歯並びがでこぼこしたところ
☑ 奥歯
また、それぞれ歯の形や歯並びが異なるので、子ども1人1人に沿った工夫が必要となってきます。
家庭でも推奨しよう
園だけでなく、家庭でも大切な「歯」。園で行っている取り組みを家庭にも共有することで、子どもが継続して意識できるほか、保護者の方もそれに対し協力することが出来ます。園で虫歯予防デーなど歯に関する取り組みを行う際には、必ず家庭との連携を取るようにしましょう。
おうちでも歯の大切さを

園での取り組みだけでは、歯の健康を守ることは出来ません。家庭でも同様に歯の大切さを伝えていく事が大切です。また、家庭でこそできる取り組みも、多くあります。保護者の方に向けて、「今、園では虫歯予防期間として歯の大切さを教えている」ということを知らせていくことが大切となってきます。
☆ 家庭に向けておすすめできる歯の取り組み
☑ 歯に関する絵本を読む
☑ 歯に良くない食べ物を実際に見せながら学ぶ
☑ 歯磨きを子どもたちと一緒にしてもらう
☑ 歯磨きに関する映像を一緒に見る
お知らせや連絡帳で連携を

上記でも少し触れましたが、家庭に対し、「今、園では何に積極的に取り組んでいるか」について発信していく事が重要です。
そのためにも、お知らせや取り組みのポスターを保護者のお迎え場所付近に貼ったり、口頭で話したり、連絡帳にまとめて書いておくことが必要となってきます。
その際、保護者の方にも正しいブラッシングについて知識を深めてもらえるような情報があるとなおいいです。園で読み聞かせている本や、製作したもの等について共有していくこともおすすめです。
最後に
「虫歯予防デー」についてまとめていきましたが、いかがでしたでしょうか。
歯の大切さを伝える際に重要なことは、「虫歯の怖さ」をいかに表現できるかです。
また、虫歯予防デーは、子どもたちにとって歯の健康を整えるのに絶好のチャンスです。この期間を機に、保育園では、正しい歯磨きや予防法を身につけさせ、園でも家庭でも気持ちよく過ごせるように指導しましょう。